はじめに
先日、このような質問がありました
どうすればもっと授業がうまくなりますか?
「うわ〜、自分も知りたい〜笑」っていう思いをグッと堪え、自分よりも若い人からの質問なので、なんとかヒントになればという思いでお答えしました。
意外にもその子は、「なるほど!」「自分もがんばってみます!」って納得して帰ってくれました。せっかくなので、みなさんにも共有できればと思い、今日は授業のうでをあげる方法について解説します。
結論は…
先に結論を申し上げると・・・
①教材研究してやってみる
②自分自身が反省した点、うまくいかなかった点、子どもがつまった点をグッドノートに書き込む
③情報収集する(先輩に聞く、本を読む、ブログを読むなど)
④良い授業を見る
の4つを自分は意識しています。それぞれについて解説します。
「①教材研究してやってみる」について
自分は、なにごともやることでうまくなると思っています。料理も、野球も、学期の演奏も、そして、授業もです。現在はYouTubeを見れば、簡単にいろいろな情報が手に入ります。でも、自分はやっぱり、プロの動画を見るよりも実際に自分でやってみるほうが学びは大きいと思っています。
ほんで、やってみたら、多くの場合100点は出ません。自分もそうで、必ず、成果も失敗もでます。でも、それでいいんだと思います。まずは、やったっていうことが大事なのだと思います。 ただし、当然だけど、行き当たりばったりの授業はだめです。子どもにも失礼だし、何よりも教材研究をしなければ力なんてつくはずがないので・・・
「②自分自身が反省した点、うまくいかなかった点、子どもがつまった点をグッドノートに書き込む」について
これは自分が若手のときによくやっていたことです。ふと、昔のものをひっぱってきました。
・結果をグラフ化したいが、点をうつのができてない。そっか折れ線グラフって4年でならうのんだな(3年:風やゴムのはたらき)
・教科書は9時から15時までの気温を調べているけど、晴れのときの気温の変わり方があまりおおきくない。だから、くもりとはれの違いがとらえにくい(4年:天気の変化)
・単元の最初に川の見学にいったけど、質の高い疑問(なんで外側が削れているの?)とか出なかった。単元の最後のほうがいい?(5年:流れる水のはたらき)
・色水に浸したけど、茎とか葉がなかなか色がつかない。時間のせい?つかってる食紅のせい?植物のせい?(6年:植物のからだのはたらき)
自分は、失敗って改善するための大事なタネだと思っています。上記の疑問は間違いなく、教材研究では気付けなかった授業をやったからこそわかる疑問だと思います。そして、これらの疑問があれば、そういう視点で授業改善に望めます。
もちろん、これは理科だけでなくどの教科でも応用できると思います。
「③情報収集する(先輩に聞く、本を読む、ブログを読むなど)」について
自分は、先輩に聞いたり、本をよんだりもよくするのですが、基本的には「②自分自身が反省した点、うまくいかなかった点、子どもがつまった点をグッドノートに書き込む」でみつかった疑問を解決するために行います。理由は、そのほうが時短になるし、効果的だからです。
例えば、ある本を読んでて、1年後とかに読むと前読んだときとは違ったところに「なるほどな」ってなることありません?あれって、その時々の自分の興味関心や授業のレベル感が違うから起きるのだと思います。
自分の授業レベルが低いときにただやみくもにインプットしていても、その作者の伝えたいことが100%理解できるわけではないのかなって思います。だから、その時々の疑問とか興味を大事にして行けばいいと思います。あと、やっぱり先輩とか本って偉大です。自分だけで考えるより絶対に人に頼ったほうがいいです。
「④良い授業を見る」について
あとは、やっぱり良い授業を見ることだと思います。なんか自分は良い授業見ると、るんるんになっちゃって、「次はどうでる?」「自分ならどうする?」って楽しくなります笑
良い授業を見るのはなぜかというと、自分の授業観が刺激されるからだと思います。
だんだん教員歴がながくなって、授業が流せるようになると、「まあこれでいいか」ってなっちゃうことがあります。なんかもったいないです。
自分は、ある人の授業見て、未だに衝撃が残っています。その人は45分で3言しか話しませんでした。「どれだけ子どもが育っているんだよ」「自分はまだまだだ…」「どうすればできる?」「できる感じがしない」って笑
あの衝撃があるから、やっぱりもっともっとうまくなりたいってなります。あの出会いは大きかったです。みなさんにもそんな出会いがあればいいなって思っています。
終わりに
授業の腕を磨くのに、近道はないです。本見たからってすぐにできるわけではないです。ただ、やれば間違いなく昨日よりは経験値は増えると思います。
だから、地道にコツコツやっていきましょう。自分もそういう方とともにもっと授業がうまくなりたいです。
🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。
▶3年生の理科授業まとめページはこちら
▶4年生の理科授業まとめページはこちら
▶5年生の理科授業まとめページはこちら
▶6年生の理科授業まとめページはこちら
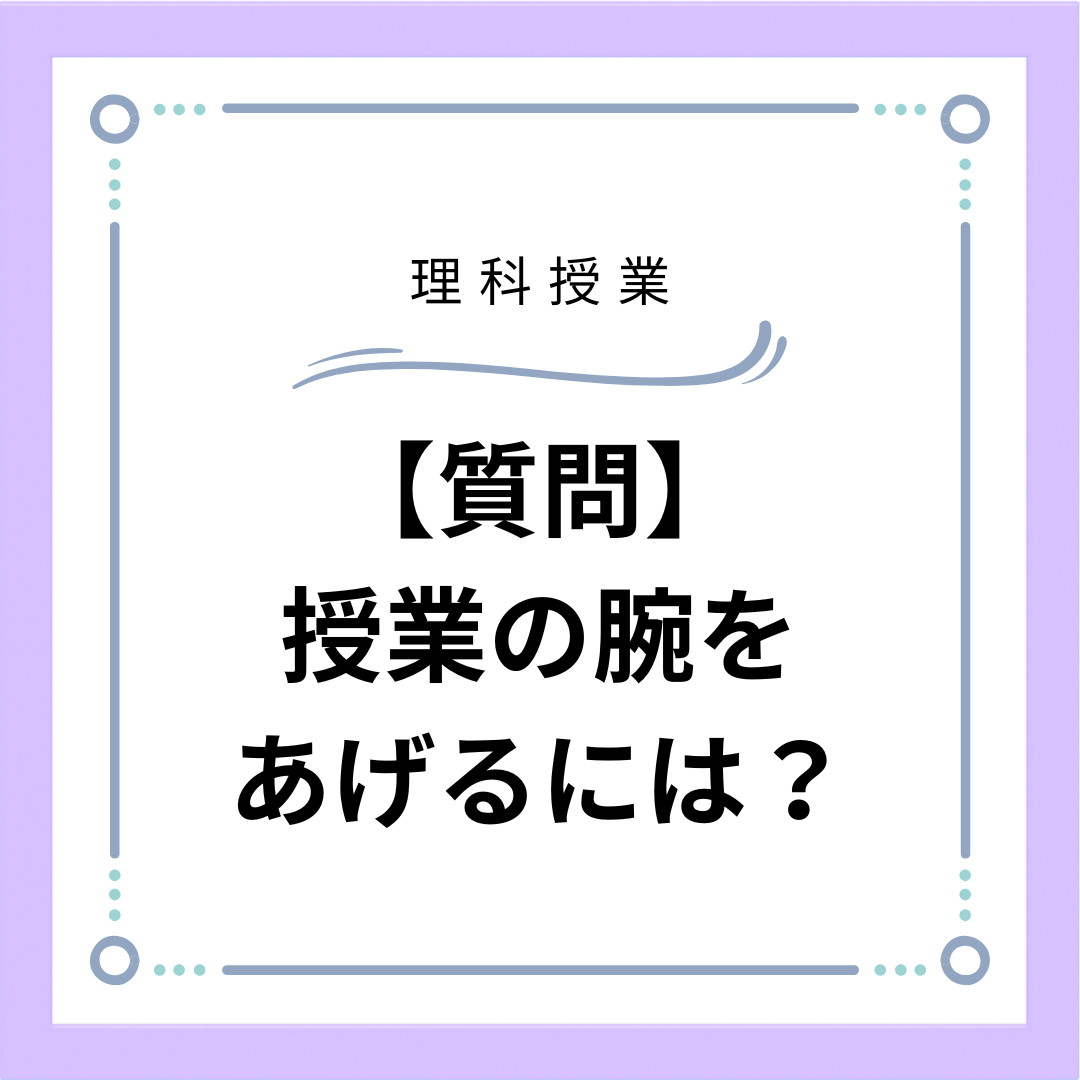
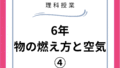
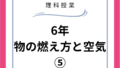
コメント