このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。
これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。
この記事を読むと、
・授業のねらいと展開の流れが分かります
・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります
・次の授業づくりのヒントが得られます
学年別にまとめた授業案はこちら👇
👉 3年理科まとめページ
👉 4年理科まとめページ
👉 5年理科まとめページ
👉 6年理科まとめページ
まだ5授業目を見ていない方は、先に6年理科「月の形と太陽」指導案に悩む先生へ|5時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「月の形と太陽」のまとめページをごらんください
<日没直後や日の出直後の月の見え方をモデル実験で確認しよう>
板書案
しばらくおまちください
ふりかえりをする
C:前の学習のふりかえりをしましょう
C:はい
C:Aさん
C:はい。前の課題は、「本当に月の形が変わるのは、太陽と月の位置が変わるからなのかな?」です
C:おなじです。はい
C:Bさん
C:前のまとめは「月の形が日によって変わって見えるのは、太陽と月の位置関係が毎日少しずつ変わっていくため、太陽の光が当たって明るく見える部分が少しずつ変わるからである」です。
C:同じです
T:そうだね。ほんで、この位置関係だったらどんな月に見えるのかっていうのも授業の後半では確認しましたね
C:はい
T:じゃあ、復習もかねて… こういう位置関係だったらどんな月に見える?
C:はい
C:できました
T:これ太陽はここにあるから、光がこう来てるわけ。そしたら、月のどこが光るかというと、右側半分が光るわけです
C:はい
T:ほんで、この人はここにいるので、この部分は見えるわけです。そうすると、明るく光って見える部分は半分だから。左側が光った、半月になるというわけです
C:あってた
T:お〜すばらしいですね。
課題を掴む
T:そしたら、この写真覚えてる?
C:はい
T:日没直後の月
C:日の出直後の月
T:そうだね。ほんで、なぜこのような月が見えるのかっていうのは、モデル実験を用いるととてもスッキリします。だから、それを今日は確認したいと思います
C:はい
T:じゃあ、今日の課題はどうする?
C:日没直後や日の出直後の月の見え方をモデル実験で確認しよう
T:じゃあ、それでいきましょう
ということで本時の課題として「日没直後や日の出直後の月の見え方をモデル実験で確認しよう」に決まりました。
日没直後の月の見え方をモデル実験をもとに確かめる
T:そしたら、この写真覚えてる?
C:はい。夕方の月の写真です。そうですね
T:ほんで、これって日にちが経つと月の明るく光る部分はどうなるんだっけ?
C:増えていく
T:そうですね。
T:ほんで、これは一応モデル実験をもとにしたら説明がつきます
C:ほ〜
T:ということでこんなものをもってきました
C:地球?
T:そうです。ほんで北ってどこかわかる?
C:ここ
T:そうそう。この上に北極星があるから、ここを北としたわけです。ほんで、北を見たとき、右側が?
C:東
T:左側が?
C:西
T:ですね。つまり、太陽はどこにあるかというと
C:ここらへん
T:そうだね。西にあるもんね
T:じゃあ、9月◯日の月を再現してみて
C:このへんかな
T:お〜いい感じ
T:ほんで、9月△日の月を再現してみて
C:このへんかな
T:ほんで、9月□日を再現してみて
C:このへんかな
T:という感じに、だんだん太陽と月の位置関係が変わると、光って見える部分がふえて、ここにおくと満月になるというわけです
C:はい
T:ほんで、それ以降は見えなくなるんだけど、それはなぜかというと
C:月が更に、進むと見えない位置に行っちゃうから
T:そうそう。だから、夕方では見えなくなるわけだね
日の出直後の月の見え方をモデル図をもとに確かめる
T:じゃあ、満月以降はいつ見えるかと言うと
C:朝!
T:そうですね。日の出直後だね。ほんで、日の出直後ってことは、太陽はどこにある?
C:東
T:そうそう。だから、今度は、こっちに観察者がくるわけよ
C:ほうほう
T:ほんで、9月✕日の月を再現してみて
C:できました
T:じゃあ、9月●日の月は?
C:できました
T:最後、9月■日の月は?
C:できました
T:という感じに、だんだん太陽と月の位置関係が変わると、光って見える部分がへっていって、ここにおくと新月になるというわけです
C:なるほど
正午の時や真夜中の時の月の見え方は?
T:じゃあ、正午のとき、太陽ってどこにおる?
C:南
T:そうだね。だから、観察者はここにくるわけ
T:じゃあ、正午のときどう見えるかと言うと
C:光って見える部分が少なくて、新月になって、だんだん光って見える部分がふえる
T:そうだね。
T:じゃあ、逆に、真夜中の時、太陽ってどこにおる?
C:地球の反対側?
T:まあ、観察者の反対側かな?つまり、ここに来るわけ
T:じゃあ、正午のときどう見えるかと言うと
C:光って見える部分がふえていって、満月になって、だんだん光って見える部分がへっていく
T:そういうことだね。そんな感じに見えるはずだよ
一直線に並んだ場合はどうなるの?
C:先生。聞いてもいいですか?
T:いいよ
C:真夜中のときって、太陽がここで、地球があって、それで月なら、地球で明かりが隠れるはずなのに、なんで満月になるんですか?
C:たしかに
T:あ〜めちゃくちゃいい質問。先生もそれ小学生の時理解できんくて…なんでやと思う?
C:うーん
T:これは難しいよね。実は、太陽と地球ってうーんと離れているのね。だから、一直線になることはあんまりなくて、どうしてもちょっと上かちょっと下にずれるわけよ。そしたら、太陽の光があたるというわけ。
C:ほう
T:ほんで、たまたま一直線になることもあります。そうなるとこんなふうにみえます。
C:なんか、かけてる
T:そうこれは、地球のせいで、この部分だけ光があたらなくて起きる現象です。これのことを月食っていいます
C:あ〜きいたことある
T:ほんで、逆に、昼間って太陽みえるやん。
C:はい
T:でも、太陽、月、地球の順で一直線になることもありえません?
C:ありえます
T:そうなると、こんなふうにみえます
C:太陽かけてる
T:そうそう。これがいわゆる日食ってやつです
C:あ〜きいたことある
T:ちょっと脱線したけど、ようは一直線にならぶことはめったになくて、上か下に少しはずれるから、それで満月に見えるってわけ
C:なるほど
ふりかえりをし、プリントをする
T:じゃあ、ふりかえりをしてみて
C:はい
C:できました
T:じゃあ、残った時間で、プリントをしましょう
C:はい
(プリント解き中)
T:じゃあ、いいかな?
C:はい
T:これで一応この勉強はおわりね。要するに、月の形の見え方は、何によって決まるの?
C:太陽と月の位置関係
T:そうだね。それで明るく光る部分が変わるから、変わって見えるというわけです
終わりに
最後は、日常に返してあげたいです。モデル実験が現実でいうとどういうことかって。あと、どうしても空間的って難しいから、子どもの疑問は説明してあげてほしいです。それによって、イメージ形成がされるのかなって思います。
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「月の形と太陽」のまとめページをごらんください
🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。
▶3年生の理科授業まとめページはこちら
▶4年生の理科授業まとめページはこちら
▶5年生の理科授業まとめページはこちら
▶6年生の理科授業まとめページはこちら
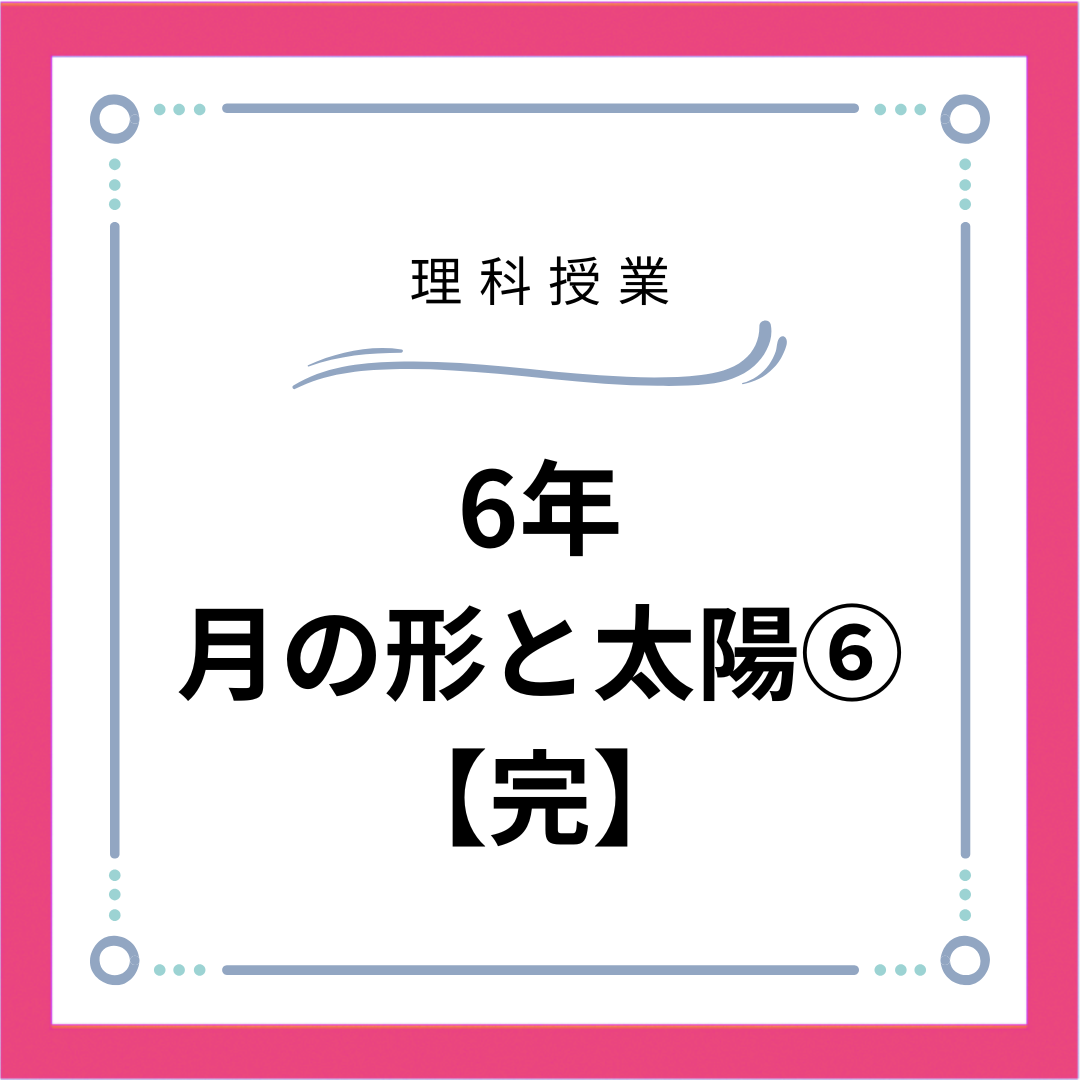
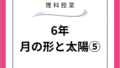
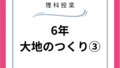
コメント