授業を変えたいと思った理由
最近ある素敵な教育書に出会いました。その本を読み終え、空いたスペースに自分は手書きでこう書きました。
理科の授業づくりで困ることが昔に比べ少なくなった。理科のテストで概ね点数を取らせてあげることができるようになった。子どもたちが楽しいと思えるような授業もできるようになってきた。でも、何かモヤモヤする。
あ〜なるほど。自分が求めているものは多分そこじゃないんだな。きっと問題解決能力を身につけさせてあげたいんだな。もっと言えば、「私の今の授業は、本当にすべての子どもたちに問題解決能力をつけられているのだろうか?」というモヤモヤなのだろうな。
もし問題解決能力がついているのであれば、なぜ自由研究があそこまですくないのだろうか?あれこそが自分の授業に対する子どもたちからのアンサーなのではないか。自分が敷いたレールに子どもたちをのせ、それで問題解決をさせているが、本当にその授業で問題解決能力がつくのだろうか?
これが私が授業を変えたいと思ったスタートです。
目指す授業について
じゃあ、これから挑戦したい授業とは何かというと、簡単に言えば「自由進度学習」です。まだ調べたばっかりなのでおかしな部分もあるかもしれませんが、自由進度学習とは、要するに「子どもが自分のペースで学習を進める方法」だと思います。
自分で問題を見つけ、自分で予想を立て、自分で実験方法を立て、自分で実験し、自分で結果を出し、自分で考察する。自分でやるのが不安なら友達を巻き込んでもいいし、実験してみて自分の予想が間違っているとわかったら友達の結果を見てもいいし、満足いかなかったら何回やってもいいし
みたいな感じです。取り組む問題も、進度も、行う実験も、誰とやるのかも全部子どもが選んでいく的な…わかんないけど、こんな授業ができたら問題解決能力がどの子にもつくのではないかってワクワクしたんです。
自由進度学習に対する課題点について
ただ、自由進度学習に対し、ぶっちゃけ悪いイメージもあります。ざっくりあげると…
◯放任に見える…子どもが自分のペースで進める=先生がおしえていないというイメージ
◯時間がかかりそう…授業時数には限りがあるけど、自由進度学習だと収まらないかも
◯進度の差が大きくなりそう…できる子はどんどん先へ、苦手な子はなかなか進めず差が広がるイメージがある
◯みとりが難しそう…1人ですべての子をみとるとなると、みきられないかなって
◯学習の穴ができそう…本人の判断で「好きな部分」ばかり進めて「苦手な部分」を避けてしまうと基礎のぬけもれが起きそう
◯協働学習がしにくそう…一人一人進度がバラバラなので、グループでの学び合いやディスカッションが成立しにくそう
などです。そして、何より自由進度学習って学びの主導権を子どもに譲る行為なので、それってめちゃくちゃ怖いなって思います。
一斉授業の場合、主導権が教師にあるので、問題や時間などをコントロールできます。たとえば、トンチンカンな予想が出た場合も、話し合わせることで、教科書通りの流れにさせることもできます。ただ、これをストップさせてきたからこそ、どの子にも問題解決能力をつけるというのができていないのかなっていう思いもあるのでなんとも言えませんがね。
最後に
とりあえず、自由進度学習のイメージを実現できれば、問題解決能力は少なくとも今よりはつくと思います。ただ、乗り越えるべき壁も多く、試していかなければならないことも多そうです。むずかしいけど、ワクワクしますね。
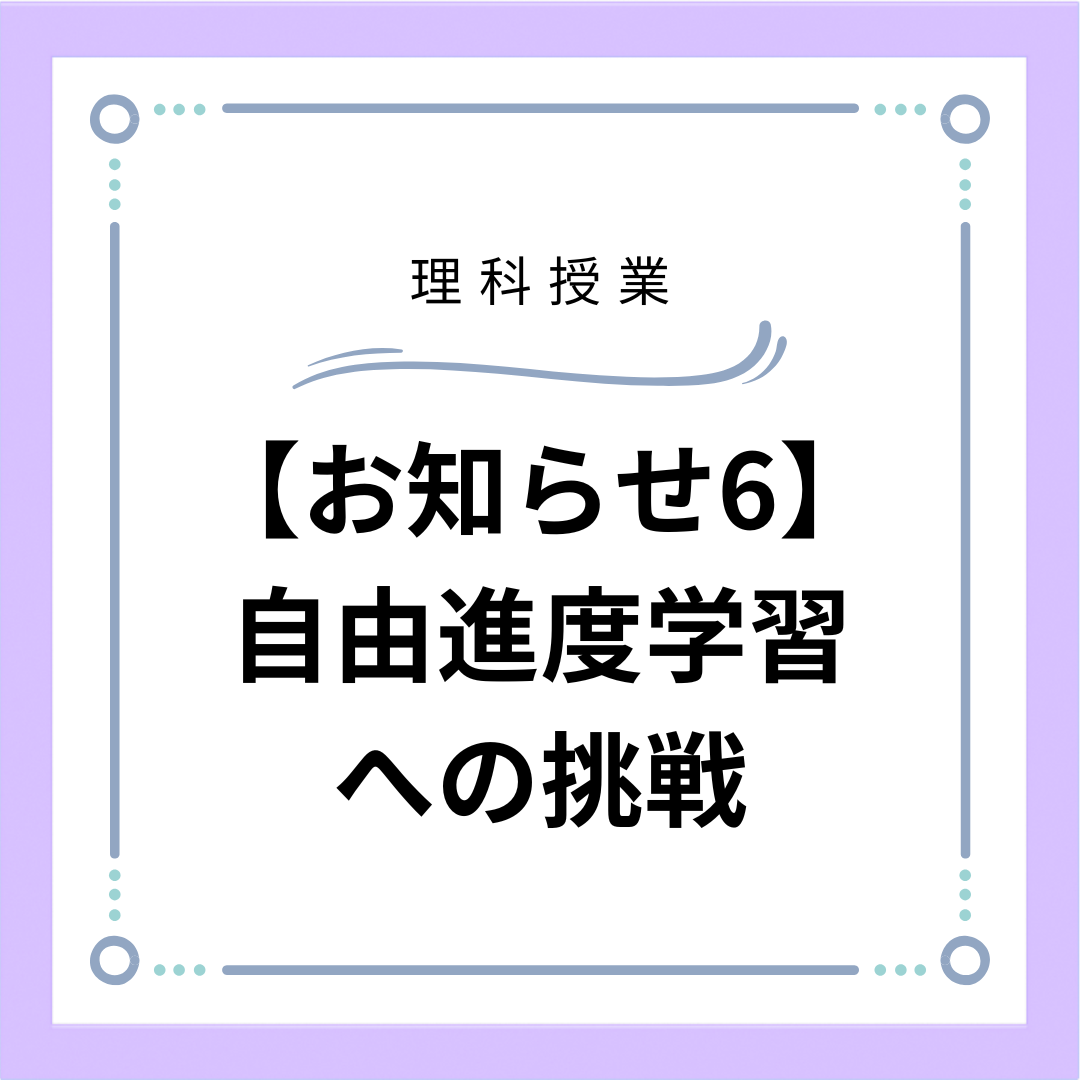

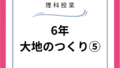
コメント