はじめに
最近、自由進度学習に興味を持っています。なぜ興味を持ったのかについては、【お知らせ6】自由進度学習を目指します!その理由と課題点について解説で紹介していますので、まだ読まれていない方は先に御覧ください。そうすると、本記事も読みやすいと思います。
さて本題に入るのですが、先週実際に自由進度学習に挑戦してみました。正直言うと、めちゃくちゃ難しかったです。いっぱい失敗しました。でも失敗から学べることってたくさんあるし、もしかしたら、自分の学びがだれかの役にたつかもしれないと思い、今回は「自由進度学習をやってみたうえで分かった子どもの実態と理科で目指すべき自由進度学習」について述べていきたいと思います。
取り組んだ自由進度学習の概要について
今回は、初めての挑戦ということもあり、1授業完結型の自由進度学習に挑戦しました。授業の流れとしては…
① 前時の復習(2分)
② 子どもたちから出た疑問の紹介、課題を確認(3分)
③ 課題を解決するために自由進度学習(35分)
④ 結論の確認と振り返り(5分)
といった感じです。理科の場合は、「不思議を自分の手で真実に変える教科」なので、振り返りで出た疑問を取り上げるというスタイルはやりやすいなと思いました。
子どもの実態について
では、子どもの実態はどうだったのかについてお伝えします。結論からと言うと…
・ネット検索で調べる
・ユーチューブや動画などで調べる
・教科書や本を見る
といった様子がほとんどでした。残念ながら実験する子は誰もいませんでした。また、初めての挑戦ということもあり、結論まで出すこともできませんでした。ただ、子どもたちは楽しそうだったし、どの子も主体的に授業に臨んでいました。
自由進度学習をやってみての1つ目の違和感について
正直言うと…自由進度学習をやってみて、子どもたちは楽しそうだったけど、授業の感想としては「全然だめだったな」という思いです。今回の授業をやってみて感じた違和感は2つあります。
1つ目は…
・これで本当に問題解決能力がつくのか?
ということです。そもそも、自由進度学習を始めた理由はなんだったかな…っていうことを考えると、子どもたちは楽しそうだし、主体的になっているけど、そこじゃないよなって思いました。
前回の記事にも述べたように、「問題解決能力をつけたい」っていうのが自分のスタートだし、問題解決能力とは、「不思議を見つけ、予想を立て、実験方法を考え、実験し、結果を出し、考察し、新しい不思議を見つける」っていう力だと思います。今回は、「実験をやっていない」「予想をたてていない」という時点でアウトだし、こんな授業だったら何回やっても問題解決能力はつかないなと思いました。
自由進度学習をやってみての2つ目の違和感について
2つ目は…
ネットに書いてあることを見つけたからと言って、理解できているとは限らない
ということです。
今回、「先生わかりました!」とか「ここに〇〇って書いてあります」っていう場面がありました。その際に「これってどういうこと?」って尋ねると多くの子が「わかりません」って言っていました。なんか思い描いていた姿とはちがうなって思いました。子どもたちは、答えを探すことに重きをおいているけど、教師は「わかった!」っていうのを目指しています。分かったとは「言葉とイメージが一致すること」だと思います。
例えば、「私の好きな食べ物は、パチュキュットです」って本に書いてあったとします。その際、「この子は何が好きなのか?」ってきかれたら「パチュキュット」っていうのはわかります。でも、「パチュキュット」っていうものを知らないから本当の意味では分かっていない(言葉とイメージが一致していない)と思います。(※パチュキュットは、自分が考えた造語です笑)
つまり、何がいいたいかというと、「本や動画の調べ学習をしたからといって分かったとは限らない」「ネットには中学校・高校レベルの情報もあるけど、答えらしきものを拾ってきて分かったっていっている可能性がある」ということです。
理科で目指すべき自由進度学習とは?
じゃあ、これらの実態を踏まえて考えなければならないのは、「理科で目指すべき自由進度学習の姿とは何か?」ということです。決して今日の授業のような姿では、OKとは言えないと思います。
「問題解決能力をつける」「どの子も分かった」ってなるという原点に戻って考えると・・・
・問題解決のサイクルを自分で回すこと
・多様な解決策が出ること
なのかなって思います。
たとえば、「水たまりの水が消えたのはどうして?」っていう不思議を見つけた時、Aさんは「染み込んだ」、Bさんは「流れていった」、Cさんは「空気中にいった」っていう予想をし、一人一人がもし自分の予想が正しいのなら、どんな実験をしてどんな結果が出たらいいのかを考え、実験して、結果を出して、考察して真実がわかりましたみたいな感じです。
そして、もっと言えば、その問題解決の過程の中で「見方・考え方」を働かせる姿があれば尚良しって感じだとおもいます。例えば、「もし空気中にいったなら、目に見えなくてもあるはずだからラップをかぶせばつかまえられるはず」(実体的な見方)みたいな感じです。少なくとも「本やネット、ユーチューブ、教科書で情報を集めるだけ」では、「見方・考え方」は働かないし、深い学びにならないし、実感を伴った理解にもならないし、「わかった!」ってならないし…って思います。
そう考えると、今一度学習指導要領を踏まえて自由進度学習のあり方とか子供の姿を考えないといけないなと思いました。
どうやって自由進度学習を実現するのか?
やってみて、自由進度学習を実現するには、「教える」という過程がやっぱり必要だということを再確認しました。今回で言えば、「問題解決」とは何かっていうこと自体が分かっていなかったから、調べ学習に走ったんだろうなって思います。
そして、今後のことを考えると「不思議をどうやって見つけるのか?」「実験方法をどうやって考えるのか?」「考察はどうかくのか?」っていうのを教えないと、自由進度学習での問題解決は実現しないだろうなって思いました。
ただ、前の自分のように、先生が「問題解決の仕方を教えただけ」だと本当の意味での問題解決能力がつかないのも事実だろうななって思います。だから…
・教えることは教える(不思議の見つけ方、実験方法の考え方など)
・自由進度でやってみる場面をしっかり作る(学んだことをもとに挑戦してみる)
・自由進度でチャレンジしたことを価値付ける(どこが良かったのか、どこが良くなかったのか)
・子どもの足りない部分を把握し、それを踏まえて教える(実験方法を立てるのができなかったのか?予想が立てられなかったのか?など)
といったサイクルを回すことが大事なのではないかと思います。
だから、「自由進度学習を全単元で行うっていうのは絶対にしない!」「そんなんしてたら問題解決能力つかないし」「授業時数足りないし」「逆に理科がわからない子増えるし」っていうのが今の私の結論です。
終わりに
改めて「学習指導要領って偉大だな」って思いました。
きっと、自由進度学習的なことは昔にもあったんだと思います。 今回の自分の実践はまさしく「活動あって学びなし」だなって思っていて、そうならないように「授業する際にこれは抑えないとだめだよ」っていうのを明確に学習指導要領は示しているんだと思います。「問題解決」とか「見方・考え方」とか…
他の教科はわからないけど、どの教科も自由進度学習を行う際は「その教科ならではの学び方」とか「その教科ならではの見方・考え方」を意識しないといけないのかなって思いました。
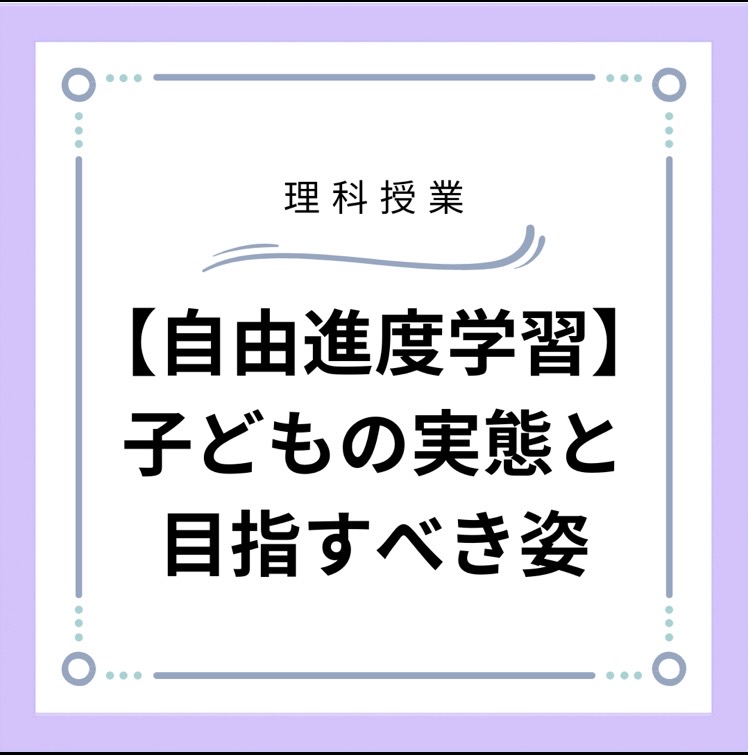
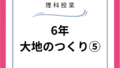
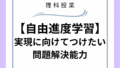
コメント