まだ前回の自由進度学習の記事を見ていない方は、先に理科専科はどう考える?! 〜自由進度学習をやってみて分かった子どもの実態と理科で目指すべき自由進度学習について〜をごらんください。
はじめに
前回の自由進度学習の記事でも述べたように、自由進度学習を実現するためには…
・教えることは教える(不思議の見つけ方、実験方法の考え方など)
・自由進度でやってみる場面をしっかり作る(学んだことをもとに挑戦してみる)
・自由進度でチャレンジしたことを価値付ける(どこが良かったのか、どこが良くなかったのか)
・子どもの足りない部分を把握し、それを踏まえて教える(実験方法を立てるのができなかったのか?予想が立てられなかったのか?など)
ということが大事だと思っています。伝えたいことは、自由進度学習がどれだけ叫ばれても、教えるという授業は絶対に必要だということです。
例えば、漢字を覚えるためにずっとアウトプット(例:テスト)するわけじゃないじゃないですか?インプット(例:漢字をノートに練習する)も必要じゃないですか。それと同じ感覚です。あくまでも自由進度学習は手段であり、問題解決能力をどの子にもつけることがゴールです。
という前提に立ったときに、まず充実を図らなければならないのは、「問題解決能力をいかにわかりやすく子どもたちに教えるのか。そして身に付けさせるのか」っていうところなんだろうなって思います。
問題解決能力とは?
問題解決能力とは、「不思議を科学的に解決する力」だと思います。具体的にはどんな力がいるのかと言うと…
①不思議を見つける力
②予想を立てる力
③実験方法を考える力
④実験する力
⑤結果をまとめる力
⑥考察する力
⑦振り返りをする力
の7つです。そして、それらの力を子どもたちが自覚的に使えるようにしなければなりません。
不思議を見つける力について
まずは、「不思議を見つける力」についてです。不思議がないと問題解決は絶対にスタートしませんからね。不思議とは…
・発芽するには何が必要なのか?
・コップの外側についた水滴はどこから来たのか?
・水たまりの水はどこにいったのだろうか?
などがあげられます。じゃあ、どうやったら不思議を見つける力がつくのでしょうか?この辺の記事が参考になるかもしれません。
予想を立てる力について
次は、「予想を立てる力」についてです。問題解決の基本は、「自分の予想が合っているのか。それとも間違っているのかを確かめること」だと思います。
多くの科学者も、「もしかしたら〇〇なんじゃないかな。うわ〜ちがった。じゃあ、△△かも?うわ〜合ってた」みたいなことをしているわけですし。ほんで、自由進度学習をするのであれば、やっぱり根拠のある予想を立てられたらいいですよね。だって、根拠のある予想のほうが真実を得られる可能性が高いわけですから。勘だったら、いつまでたっても真実にたどり着かないかもしれないですし。ちなみに、根拠のある予想とは…
・もしかしたら、水がいるのかもしれない。だって、生活科のときに水をあげたら大きく育ったし、水をあげなかったら枯れたもん
・もしかしたら、水蒸気かもしれない。だって、ガラスのコップの中の水が染み出るなら、漏れてることになるから大変だし、前の授業で空気中に水蒸気が出ていったなら、もどるかもしれないじゃん
などがあげられるとおもいます。じゃあ、どうやったら予想を立てる力がつくのでしょうか?この辺の記事が参考になるかもしれません。
実験方法を考える力について
次に「実験方法を考える力について」です。自分の予想を確かめるための実験であればいいので、実験方法は決して1つとは限りません。教科書と違う実験方法でもそれで確かめられそうならいいよねってことになります。あと、大事なのは条件制御ですね。「2つ条件が変わったら、どっちの条件が結果に起因したのかわからない。だから、問題解決では1つずつしかできない」っていうことですね。
正しい実験が立てられれば自分の予想の真偽を確かめれますし、複数の実験方法が思いつけば、多面的な考察につながります。実験方法とは…
同じくらいの背丈の植物を準備して、片方には水をあげ、もう片方には水をあげない。そしたら、水ありのほうが大きく育つはずだ
などがあげられると思います。じゃあ、どうやったら実験方法を考える力がつくのでしょうか?この辺の記事が参考になるかもしれません。
実験する力について
次に「実験する力について」です。まず実験器具をただしく使える力が必要だと思います。顕微鏡はこんなふうに使う、虫眼鏡はこんなふうに使うなどのことです。
ちなみに、実験器具の技能を高める場面で自由進度学習はできると思いますけど、わざわざ自由進度学習にしなくてよくない?って私は思います。わけは、自由進度にするより教師が教えるほうが早いと思うからです。そして、なにより浮いた時間を「子供が教師の手を借りずに問題解決をするという自由進度学習の時間に使いたい」って思うからです。この辺は、私の考えなので参考程度に笑
あと、実験器具の技能だけでなく、実験器具を選択する力もつけたいですよね。教師が「これを使ってね」っていうんじゃなく、必要な道具を考え自分で準備するみたいな感じです。
この辺の参考になる記事は、今のところないので随時増やしていきます。
結果をまとめる力について
次に、「結果をまとめる力について」です。グラフ、表、写真、動画、言葉など結果をまとめるための手段は色々あります。結果は、自分の考察に対しみんなが納得するための根拠となる部分なので、相手がわかりやすいと思うようなまとめ方をできたらいいですよね。今は、どの子も1台端末あるわけですし。
この辺の参考になる記事は、今のところないので随時増やしていきます。
考察する力について
次に、「考察する力について」です。考察にはいろいろな役割がありますが、絶対に大事にしてほしいのは「真実はこうです」っていうのを書く場面だということです。自分の予想が正しい場合も、自分の予想が間違っている場合も結果をもとに考察できたら花丸ですね。
そこから発展して「これが真実ならきっと〇〇もいえるのではないか?」とか「〇〇になったのは、△△が原因としてあげられるので、✕✕したらいいのではないか?」とかもできたら更に良しです。もっと求めるなら、「(実験方法が不十分だった場合)でも、この実験だと〇〇って可能性も捨てきれないんじゃないっていわれた。たしかに、条件制御たりてないかも。じゃあこうすればいいかな」とか「〇〇と△△という根拠から、✕✕が真実に違いない」みたいな「多面的」もできたらいいですよね
この辺の参考になる記事は、今のところないので随時増やしていきます。
振り返りをする力について
最後に「振り返りをする力について」です。ここでは、自分の問題解決の過程を振り返ることと、新しい不思議を見つけること、そして、問題解決を通してわかったことをアウトプットすることなどがあげられるかと思います。
この辺の参考になる記事は、今のところないので随時増やしていきます。
終わりに
さて、こんな風にまとめてみると、問題解決能力って深くないですか?そして、これらの力って本当に教えずに自由進度学習でつくのかなって私は思います。やっぱり教えるというステージは必要です。
でも、これらの問題解決能力がついた子どもたちと「教師の手を借りずに問題解決をするという自由進度学習」ができたら、すげぇ〜楽しそうだなって思います。めちゃくちゃ活発な授業です笑
そんな授業をしたいなって… 自分の夢です。ちなみに、私が目指す授業については、理科専科はどう考える?! 〜理想の授業とは?〜でご確認ください。
今後は、この辺の記事を充実させたいですね。
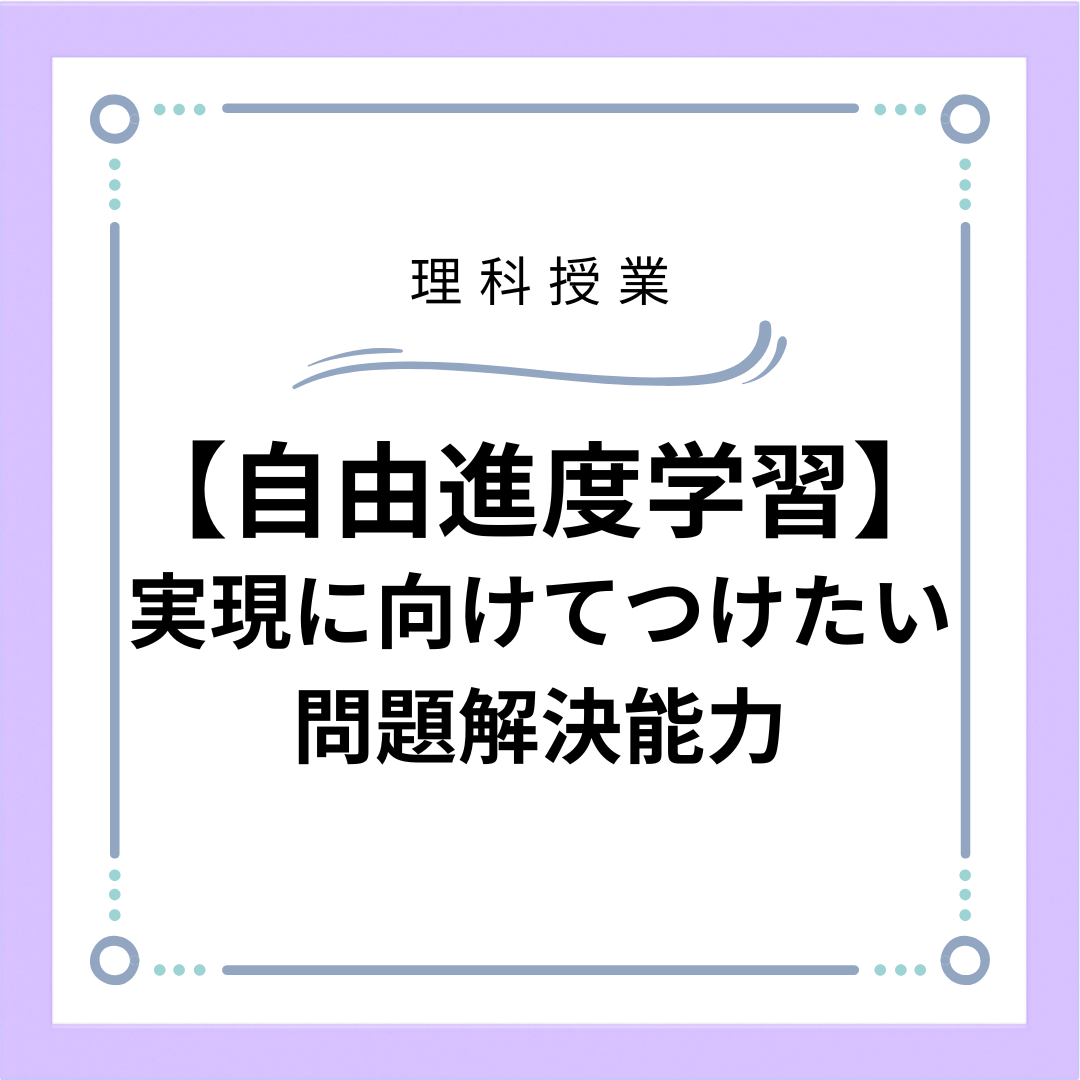

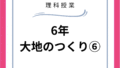
コメント