このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。
これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。
この記事を読むと、
・授業のねらいと展開の流れが分かります
・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります
・次の授業づくりのヒントが得られます
学年別にまとめた授業案はこちら👇
👉 3年理科まとめページ
👉 4年理科まとめページ
👉 5年理科まとめページ
👉 6年理科まとめページ
まだ1授業目を見ていない方は先に6年理科「電気と私たちのくらし」指導案に悩む先生へ|1時間目の授業実践からヒントを!をごらんください
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「電気と私たちのくらし」のまとめページをごらんください
<本当に光を強くしたら豆電球は明るくなるのかな?>
板書案
作成中
振り返りをする
C:前の学習の振り返りをしましょう
C:はい
C:Aさん
C:はい。前の課題は、「手回し発電機で発電をしてみよう」です
C:同じです。他にあります
C:Bさん
C:はい。前のまとめは、「手回し発電機のハンドルを回すと、発電することができる。ハンドルを速く回すと電気の働きが大きくなる」です
C:同じです
T:そうだね。ちなみに、発電ってなんやったけ?
C:電気を作ること
T:そうだね。じゃあ、今日はこの続きからしましょう
C:はい
光電池を用いて、発電をしてみる
T:そしたら、今回はこれを持ってきました
C:太陽光発電のやつだ
T:そうです。これのことを光電池って言います
C:光電池
T:ということで、今回はこれを使って発電をさせてみましょう
C:はい
T:じゃあ、集合
C:はい
T:そしたら、こっちがプラス極でこっちがマイナス極です。こんなふうに回路を作ります。ほんで、できたら
C:日光をあてる
T:そうだね。それで本当に発電できるのかを確認してください
C:はい
T:じゃあ、グループで1こずつもっていってください
C:はい
T:じゃあ、はじめていいよ
C:よし、回路できた
C:日光に当ててみよう
C:あれ?
C:あ!ついた
課題を掴む
T:そしたら、一旦もどりましょう
C:はい
T:どうだった?
C:明かりがつきました
T:ということは発電…
C:できた
T:ということですね
C:はい
T:じゃあ、今日考えてほしいのは、前回手回し発電機のとき、何を変えたら豆電球もっと明るくなった?
C:回す速さ
T:そうだよね。じゃあ、光電池だったらどうやったらもっと明るくなるかな?ペアで相談
C:はい
C:できました
T:おしえて
C:はい
T:Cさん
C:はい。もっと光を強くしたら明るくなると思います
C:おなじです
T:そっか!でも本当に光強くしたら明るくなるんかな?
C:たぶん
T:じゃあ、今日はそれについてしらべていこう。ということで今日の課題は?
C:本当に光を強くしたら豆電球は明るくなるのかな?
T:じゃあ、それで
ということで本時の課題として「本当に光を強くしたら豆電球は明るくなるのかな?」に決まりました。
実験方法を確認する
T:じゃあ、実験方法の確認ね。今回光を強くするために、これを使います
C:鏡
T:どうするんだと思う?
C:はい
T:Dさん
C:はい。鏡で日光を重ねて、光を強くするんだと思います
C:おなじです
T:そうだね。3年生のときにやりましたね。
C:はい
T:ということで、A(日光だけのとき)とB(日光+鏡で日光を集めたとき)で比べてみましょう
C:はい
T:もし皆さんの予想が正しければ
C:日光+鏡で日光を集めたときのほうが明るくなるはず
T:ですね。質問ありますか?
C:ないです
T:そしたら、比較のためには光電池が2こあったら良いと思うので、こことここで1チーム。こことここで1チーム。こことここで1チーム。こことここで1チームって感じにします。どっちの光電池に日光を当てるのか決めてください
C:できました
T:じゃあ、鏡はここにあるのでもっていってくださね。では、はじめましょう
実験する
C:じゃあ、当てるよ
C:どう?
C:うーん。びみょう
C:先生。鏡の枚数って増やしてもいいですか?
T:いいよ
C:じゃあ、3枚くらいにしよう
C:あれ?
C:こっちのほうが明るくない?
C:うん。あかるい
結果を確認し、この結果から言えることを確認する
T:じゃあ、そろそろいいかな?
C:はい
T:じゃあ、どうだった?おしえて
C:はい
T:Eさん
C:はい。日光+鏡で日光を集めたときのほうが明るくなりました
C:同じです
T:どのチームも?
C:はい
T:ということはこの結果からどんなことが言えますか?ペアで相談
C:はい
C:できました
T:おしえて
C:はい
T:Fさん
C:はい。光が強いほうが、豆電球が明るくなるとわかりました
C:同じです
T:光が強いとなんで明るくなるんかな?
C:はい
T:Gさん
C:はい。光が強いとたくさん発電できるからだと思います。
C:同じです
T:じゃあ、本当にたくさん発電できてるのか検流計で確かめてみましょう
C:お〜
T:まず、日光だけのとき
C:1.7Aくらい
T:じゃあ、日光と鏡で日光を集めたとき
C:あ!2.3A
T:ということは、電流が大きくなってるね
C:すごい
まとめをし、振り返りをする
T:じゃあ、今日の課題に対するまとめはどうする?
C:光を強くしたら豆電球は明るくなる
T:ですね
といって本時のまとめとして「光を強くしたら豆電球は明るくなる」と書きました。
T:ちなみに、教科書のここに、光電池に光を強く当てると、電気の働きが大きくなりますってかいてあるからやっぱりそうみたいだね
C:はい
T:じゃあ、振り返りをしましょう
C:はい
C:できました
おわりに
どこに焦点化をさせたいかっていうのが大事かなって思います。今回で言えば、「もっと明るくするには?」って言う部分にしました。ここをつつくことで「もっと光を強くすれば」という量的な見方が使ってくれるのではないかと考えたからです。
また、感覚だけでなく、検流計を用いることで「数」として、電流が大きくなっていることを捉えることも大事なことだと思います。
続きが気になる方は、6年理科「電気と私たちのくらし」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をごらんください
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「電気と私たちのくらし」のまとめページをごらんください
🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。
▶3年生の理科授業まとめページはこちら
▶4年生の理科授業まとめページはこちら
▶5年生の理科授業まとめページはこちら
▶6年生の理科授業まとめページはこちら
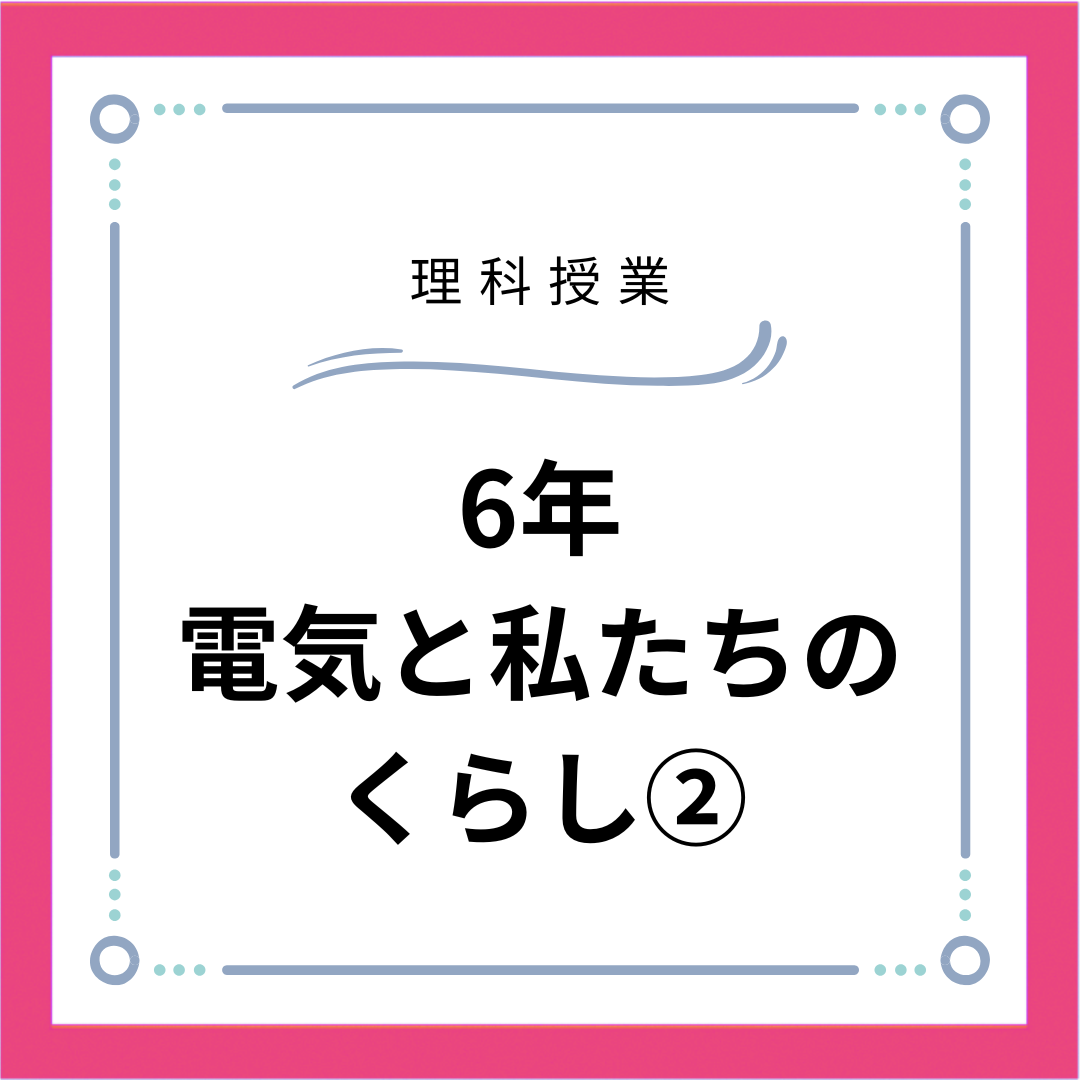
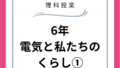
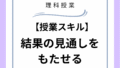
コメント