このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科であるぼん先生が、実際の授業をもとに作成したセリフ形式の理科授業を紹介しています。
これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。
この記事を読むと、
・授業のねらいと展開の流れが分かります
・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります
・次の授業づくりのヒントが得られます。
学年別にまとめた授業案はこちら👇
👉 3年理科まとめページ(全単元・全授業完成済み)
👉 4年理科まとめページ(全単元・全授業完成済み)
👉 5年理科まとめページ(「魚の誕生」の板書以外全単元・全授業完成済み)
👉 6年理科まとめページ(頑張って作成中!)
まだ2授業目を見ていない方は先に6年理科「水溶液の性質とはたらき」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「水溶液の性質とはたらき」のまとめページをごらんください
<炭酸水には何がとけているのかな?>
板書案
作成中です
ふりかえりをする
C:前の授業のふりかえりをしましょう
C:はい
C:Aさん
C:はい。前の課題は「5種類の水溶液を蒸発させるとどうなるのかな?」です
C:おなじです。はい
C:Bさん
C:はい。前のまとめは「食塩水と重曹水から水を蒸発させると、白い物(固体)が出てくる。5種類の水溶液のうち、食塩水と重曹水は固体がとけた水溶液である。」です
C:同じです
T:そうだね。そしたら、今日は何をするの?
C:炭酸水には何が溶けているのかを調べる
T:そうだね。じゃあ、今日の課題はどうする?
C:炭酸水には何がとけているのかな?
T:じゃあ、それでいこうと
ということで本時の課題として「炭酸水には何がとけているのかな?」にきまりました。
予想をする
T:じゃあ、予想を立ててみてください。根拠のある予想を立てるときに大事なことは?
C:日常生活とつなげる
C:既習とつなげる
T:ですね。ちなみに、固体ではありません。固体なら蒸発したときでてくるから
C:うーん
C:できました
T:じゃあ、グループで相談
C:はい
C:できました
T:おしえて
C:はい。
C:Cさん
C:はい。私は空気だと思います。わけは、水の中で空気をブクブクさせたら、泡がみえたのでそれと同じだと思ったからです
C:わかりました
C:ほかにあります
C:Dさん
C:はい。自分は窒素だと思います。わけは、炭酸水ってたくさんウッているから、窒素もたくさんあるし、それで使われているのではないかと思ったからです
C:わかりました
T:空気と窒素っておなじ?
C:いや、ちがいます
T:どう違うの?
C:空気は窒素も酸素も二酸化炭素も入っていて、窒素だと窒素だけです
T:そうだね。つまり、これはぜんぜん違うよ
C:あ〜、先生ちょっと変えたいです
T:どれに?
C:窒素です。理由は空気だったら、酸素が入っているから、火を近づけたらボッってもえてしまうので、変かなと思ったからです
C:あ〜たしかに
T:たしかに。二酸化炭素にはしないの?
C:うーん。量がすくないから…
T:なるほどね
T:じゃあ、選択肢は?
C:空気
C:窒素
C:二酸化炭素
T:ほかにもあるよ
C:酸素
C:あぶなくない?
T:予想だからいいの。あとは、その他ね。
C:はい
T:じゃあ、いろんな意見聞いたうえで、ネームプレートはりにきて
C:はい
T:なるほどね。
実験方法を考える
T:じゃあ、実験方法ね。まずは、水上置換法であわを集めます。図でいうとこんな感じ。
C:え〜こんなんであつまるんですか
T:それがね〜 あつまるんですよ笑
T:ほんで、こんなふうに泡をあつめた試験管を準備します
T:じゃあ、この後どんな実験して、どんな結果になれば真実わかるかな?ペアで相談
C:はい
C:できました
T:おしえて
C:はい
T:Dさん
C:はい。火のついた線香を試験官の中にいれ、燃えたら酸素か空気で、燃えなかったら窒素か二酸化炭素かその他です
C:同じです
C:ほかにあります
C:Eさん
C:はい。石灰水を入れてみて、白く濁ったら二酸化炭素です。変わらなかったら、窒素かその他です
C:わかりました
T:ほかありますか?
C:ないです
T:おっと!酸素か空気かはどうやってしらべる?
C:うーん
C:はい
T:Fさん
C:はい。気体検知管で数値を調べればいいと思います
C:わかりました
T:いいね。
T:じゃあ、とりあえずどれする?
C:線香をいれてみる
T:そうだね。それしてみてから、次の実験考えようか
C:はい
実験する
T:じゃあ、まずは泡を集めよう。教科書みながらでいいので、道具の準備をしてね
C:はい
C:できました
T:じゃあ、やってみて
C:あ〜すごい
C:できました
T:じゃあ、集合
C:はい
T:そしたら、これ酸素集めた試験管なんだけど、みててね
C:あ〜、もえた
T:今線香どこにおいてた?
C:試験管の口のちょっと上くらい
T:それで十分結果わかったね。だから、火は、中に線香をいれないでね。あぶないから
C:はい
T:じゃあ、線香とチャッカマンもっていって
C:はい
C:やっていいですか?
T:いいよ
C:燃えない!!!
T:どうやった?
C:燃えませんでした
T:燃えたチームは?
C:0です
T:じゃあ、つぎどうする?
C:石灰水
T:じゃあ、石灰水もっていって
C:はい
C:やっていいですか?
T:いいよ
C:あ〜白く濁った
C:ということは・・・
T:言わないでね笑 じゃあ、一回席戻るよ
C:はい
結果を確認する
T:じゃあ、ワークシートをくばります。もらったら名前をかいてね
C:できました
T:じゃあ、結果を書いていくね。まずはどんな実験した?
C:線香の火を火を近づけました
T:結果は?
C:線香の火が消えました
T:そうだね。次はどんな実験した?
C:石灰水をいれました
C:結果は?
C:白く濁りました
T:ですね。
振り返りをする
T:じゃあ、今日はそろそろ時間来るので終わります。最後に振り返りをしてね
C:はい
C:できました
T:次回は何するの?
C:考察
T:ですね
終わりに
実験方法の書き方が、多面的に調べる際には意識しています。
まずはこの実験する。そうすると、これとこれに分けられる。じゃあ、次はこの実験する。そうすると、これとこれに分けられる…みたいな感じです
これができるようにしてあげたいですね
続きが気になる方は、6年理科「水溶液の性質とはたらき」指導案に悩む先生へ|4時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「水溶液の性質とはたらき」のまとめページをごらんください
🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。
▶3年生の理科授業まとめページはこちら
▶4年生の理科授業まとめページはこちら
▶5年生の理科授業まとめページはこちら
▶6年生の理科授業まとめページはこちら
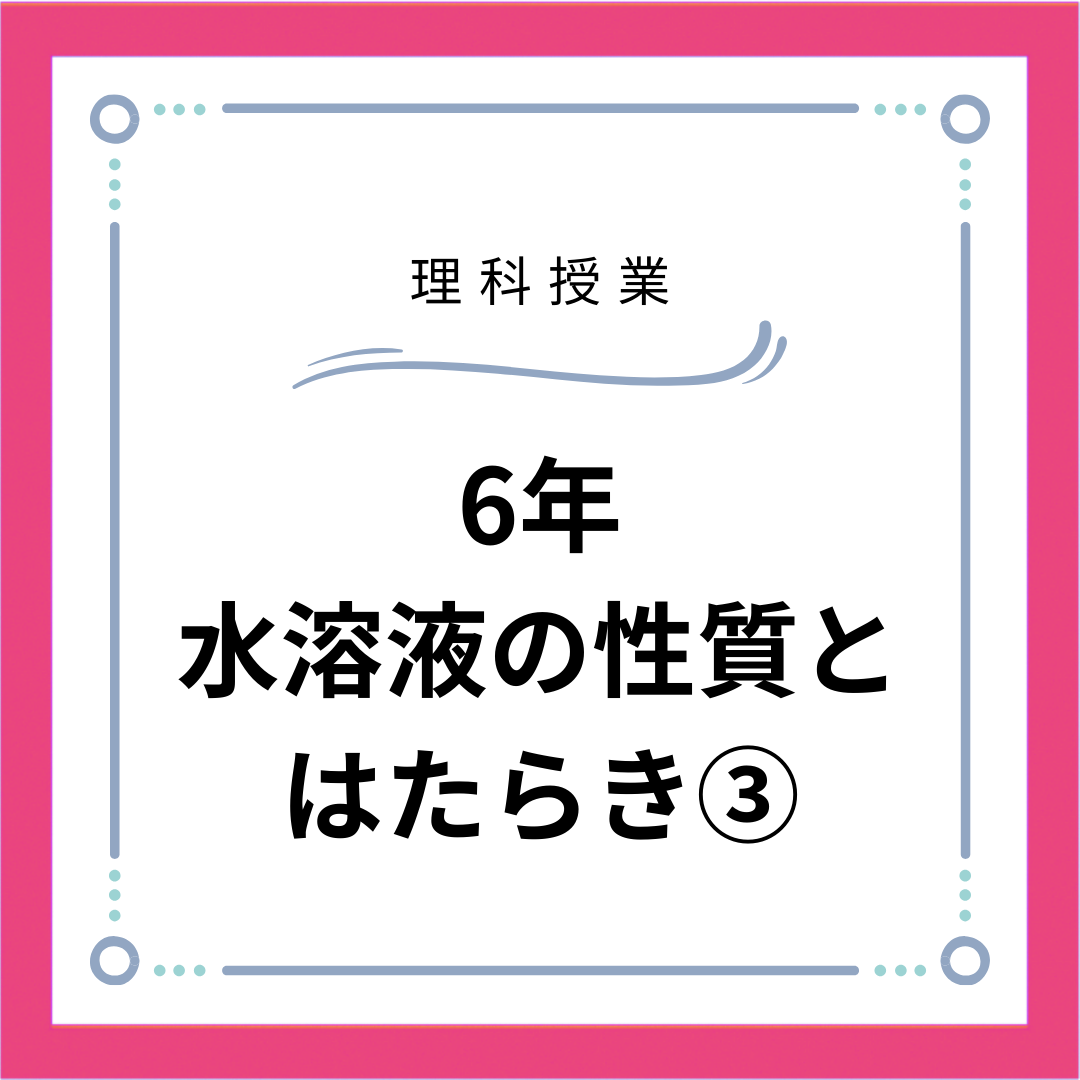
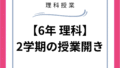
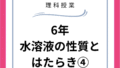
コメント