こんな質問がきました!
この前、こんな質問をもらいました。
子どもが予想を出したときに、自分の想定した予想と違うやつが出てきます。そのときに、授業時間もないので、話し合いでその子の予想を消したいのですが、なかなかうまくいきません。どうすればいいですか?
この質問を見て、「わかる〜〜〜〜〜!自分もよくあった」って思いました。例えば、こういうやつですよね。
【6年 植物のからだのはたらきにおいて】
T:子葉がしぼんだ後、植物ってどうやって養分を得ているんだと思う?予想してみて。(5年で、植物が大きく育つには日光と肥料って習っているから、それとつなげた予想が出そうだな)
C:はい。土から養分をもらっていると思います。
C:水から養分を得ているんだと思います。
C:日光に当たると養分ができるんだと思います
T:どの意見が一番あやしいかな?
(相談中)
T:(うーん、全然まとまらないな)ねえ〜5年のときに、日光があると大きく成長するって勉強しなかった?日光が怪しいんじゃない?
C:う〜ん
T:ねえ、たしかめてみよう
C:は、はい
T:(あ〜、強引にもっていってしまった)
これ自分もよくやってしまっていたので、気持ちはよくわかります。そして、これについては、めちゃくちゃかんがえてきたので、自分なりの答えがあります。今日は、それについて話します。
【答え】話し合いで予想をしぼるのは、しません!
まずはじめに、質問者は、「話し合いで授業のまとめにつながるような予想(=上記の例で言えば日光)にしぼりたい」って思いがあるみたいなのですが、結論から言うと…
私ならそれはしません!
その理由は大きく分けて、3つあります。
その理由は・・・
理由は3つあります。
①話し合いで絞るのは難しいから
自分も「より説得力がある仮説はどれかな?」とか「これってここが変じゃないかなっていうのを話し合ってみて」みたいに声掛けを変えながら、やってみたのですがなかなかうまくいきませんでした。どうやら根拠をもって否定をするっていうことや、否定を受け入れるっていうことはなかなか難しいみたいです。だから、時間がかかるけど、あまり教育的効果が薄いように感じます。(もちろんこの時間は、自分は必要だとは思っていますが・・・)
②理科に対する取り組み姿勢が主体的にならない
子どもたちはいつも全力です。もちろん変な意見が出ることもありますが、その子の意見はその子なりに一生懸命考えたものだと私は思います。だから、なんとか大事にしてあげたいという思いがあります。
また、話し合いで1つの意見に絞る時、たいていの場合、賢い子が論理的に否定をし、あまり賢くない子がそれを受け入れるっていう構図になりがちです。自分はそういう学級風土は好きではありません。どれだけもっともらしい理由だったとしても、真実がそうとは限らないというところに理科のおもしろさがあるからです。だからこそ、多様な意見(ときには間違ったものも混じったもの)が出るのが好きです。
特に6年では「多面的」という考え方を使うのですが、そのためには子どもたちの多様な意見が欠かせません。
③子どもの素朴概念が変わらないから
どれだけ動画を見せても、どれだけ正しい知識を伝えてもしばらくするとまちがった知識にもどってしまうということがよくあります。いわゆる素朴概念(日常生活の中で自然に身につけている直感的な考えや理解のこと EX:重いものほど速く落ちるなど)に戻っちゃうってやつですね。
自分は授業者として正しい知識を持たせたいと思っています。しかしうまくいかないときがあって、それはたいてい「心が動いていない」ときにおきます。動画を見せたり、話し合いで1つの予想にまとめたりするのがその代表例だと思います。
やっぱり理想は、実験して自分の目で真実を確かめる時に一番心が動きます。だからこそ、誤概念がある場合は、多少時間をかけてでも、実験をさせたいなって思います。
じゃあ、どうするのか?
じゃあ、どうするのか? 質問者の思いは予想で絞るですが、私は予想は多様であればいいと思っています。でも、時間がかけられないのなら話し合いで絞るのではなく…
実験をして、自分の目で真実を確認させる
というのが一番速いと思います。
どういうことかというと・・・先程の、6年植物のからだのはたらきを例にしてあげると
T:土や水や肥料の中にデンプンがあるっていう説と日光に当たるとデンプンができるって説があるんだね
C:はい
T:そしたら、これどんな実験したら解決する?
C:うーん
T:今までの学習でデンプンがあるか調べるとき何使ってた?
C:ヨウ素液
T:ヨウ素液使って実験できないかな?
C:かける?
T:もう少し詳しく教えて
C:うんと、水にヨウ素液をかけるで、もし水にデンプンがあるなら色が青紫色になるはずで、なければ色は変わらないはずです
T:なるほどね。この実験どう?
C:たしかに
T:この実験で調べられそうなやつって他にある?
C:土と肥料もできそう
T:じゃあ、やってみようか
(実験中)
T:どうだった?
C:色変わらなかった
T:そうだね。ということは、土や水や肥料にはデンプンは
C:ない
T:これ意外だよね。じゃあ、書こうね
といった感じです。
理科はどんな教科なのかって言ったら「不思議を自分の手で真実に変える教科」だと思います。だからこそ、私は予想ではなく実験で子どもの考えを否定してあげることが大事だと考えます。これが、速いし、楽しいし、深い理解にもつながると思います。
終わりに
「言葉じゃなく実験で否定してあげる」っていうのが私の授業観の1つです。
この発想をしてから、予想を聞くのが楽しくなりました。そして、どんな予想が来ても、「どんな実験をしてあげたら納得するかな」っていうのを考えればいいので簡単になりました。
さらに、この発想法の良いところは、「来年にもつかえる」ということです。教科書にはない予想が出たらあせるけど、間違った予想に対する実験方法を作れれば、が次の年に同じような予想が来ても余裕で対処できます。そうなれば怖いものなしです。
ぜひ、参考になれば幸いです。

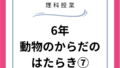

コメント