このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。
これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。
この記事を読むと、
・授業のねらいと展開の流れが分かります
・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります
・次の授業づくりのヒントが得られます
学年別にまとめた授業案はこちら👇
👉 3年理科まとめページ
👉 4年理科まとめページ
👉 5年理科まとめページ
👉 6年理科まとめページ
まだ2授業目を見ていない方は、先に6年理科「生き物どうしのかかわり」指導案に悩む先生へ|2時間目の授業実践からヒントを!をごらんください
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」のまとめページをごらんください
<どの生き物も食べ物のもとは植物なのか?>
板書案

復習し、課題を掴む
C:前の学習のふりかえりをしましょう
C:はい
C:Aさん
C:はい。前の課題は「魚は何をたべるのか?」です
C:同じです。他にあります
C:Bさん
C:はい。前のまとめは「魚は、水の中の小さい生き物をたべる」です
C:同じです
T:そうだね。たとえば何がいたかな?
C:ミジンコ
C:ミドリムシ
C:ゾウリムシ
T:なるほどね。じゃあ、今日はこの続きからしましょう
C:はい
T:そしたら、1回目の授業のときに、あともう一つ不思議がありましたね。なんでしたか?
C:どの生き物も食べ物のもとは植物なのか?
T:ですね。これってどういうことかというと。ライオンは何を食べる?
C:シマウマ
T:じゃあ、シマウマは?
C:草
T:カマキリは?
C:チョウ
T:蝶の幼虫は?
C:葉
T:っていうふうに、どの動物も食べ物のもとをたどると最後は?
C:植物にあたる
T:ですね。じゃあ、これってどんな動物にも当てはまるのかな?
C:うーん
T:ということでこれについて今日ははっきりさせましょう。じゃあ、今日の課題は?
C:どの生き物も食べ物のもとは植物なのか?
T:じゃあ、それでいこう
ということで本時の課題として「どの生き物も食べ物のもとは植物なのか?」に決まりました。
ワークシートの使い方を確認する
T:そしたら、ワークシートを配ります。もらったら名前をかきましょう
C:はい
C:できました
T:そしたら、今回いろいろな動物がありますね
C:はい
T:まずは、この中から1匹動物を選びます。ほんで、そいつが何を食べるのかを調べます
C:はい
T:ほんでたとえば、モズがバッタを食べるかどうかを調べたい時、なんて調べたらはやそうかな?ペアで相談
C:はい
C:できました
T:おしえて
C:はい
T:Cさん
C:はい。「モズ 食べ物」です
C:わかりました。他にあります
C:Dさん
C:はい。「モズ バッタ 食べるのか?」です
C:わかりました。他にあります
T:そしたら、今2パターン出てきたけど、どっちが早いと思う?
C:モズ バッタ 食べるのか
T:じゃあ、やってみるよ
C:あ!出てきた
T:本当だね。ほんで、AIが出てきたときは、ここに参考資料があるから、これを見て、確かにそうだなってなれば書いていいです。
C:わかりました
T:結構はやかったですね
T:じゃあ、もず 食べ物 だったらどうかな?
C:パッとは見つからなさそう
T:そうだね。今回は、それぞれの動物の関係性が知りたいので、「モズ バッタ 食べるのか」みたいにしたほうが早いと思います
C:はい
T:ほんで、記録するときは、「食べるもの←食べられるもの」っていうふうにしてください。イメージは、食べられるものが食べるもののお腹に入るみたいな
C:あ〜
T:だから、モズとバッタだったら?
C:モズ←バッタ
T:ですね。逆にしたらだめですよ
C:はい
T:じゃあ、はじめてください
C:はい
調べ学習をする
C:え〜意外
C:これもそうなんだ
T:お!そうですね。その動物が何を食べるかって1個とは限りませんからね
C:へ〜
C:ほんまや
T:じゃあ、そろそろいいですかね?
C:はい
T:じゃあ、3つのチームに分かれて、これにどんどん矢印をつけていってください
C:はい
C:できた
C:なんかすごい
T:じゃあ、もってきてね
C:はい
T:お〜いいかんじですね
わかったことを確認する
T:じゃあ、この結果からどんなことが言えますか?ノートにかいてみてください
C:はい
C:できました
T:おしえて
C:はい
T:Eさん
C:はい。もとをたどっていくとやっぱり植物にあたります
C:おなじです
T:そうだね。じゃあ、なんで植物にあたるのかわかる?
C:うーん
T:ヒントは、植物のからだのはたらきでやったよ
C:あ〜、植物は自分でデンプンを作れるから?
T:お!するどい。正解だよ。実は、植物は自分で養分が作れるけど、動物は自分で養分をつくることができないので、食べて養分を得ます。だから、もとをたどると最後は植物になるってわけ
C:先生。小さい生き物もですか?
T:そうだね。たとえば、ミカヅキモとかボルボックスも、養分を作ることができます
C:へ〜
T:じゃあ、他にわかったことありますか?
C:はい
C:Fさん
C:はい。トカゲとかバッタは、食べたり食べられたりしています
C:同じです
T:そうだね。食べたり、食べられたりしているね。ちなみに、食べるやつと食べられるやつだったら、どっちの方が数多いと思う?
C:食べるやつ。
T:え〜なんで?
C:だって、食べられたら減るもん
T:実はね、こんなふうになります
C:え〜
T:じつは、食べるやつになればなるほど数は減っていくということが分かっています
C:え〜意外
T:結局、食べるやつが多いと、食べられるやつが減って、餓死してしまうんですよ
C:あ〜
T:だから、ちょうどいいバランスになると、こんなふうな数になるらしいよ
C:へ〜
T:ほかにありますか?
C:はい
C:Gさん
C:はい。なんか生き物の世界は、複雑に絡み合っているということがわかりました
C:わかりました
T:どういうこと?もう少し詳しくおしえて
C:はい。なんか食べられたり食べたりするのがいろんなところで起きていて、複雑だなって思いました
T:なるほどね。確かに
まとめをする
T:じゃあ、まとめをしようか
C:はい
T:まとめはどうする?
C:食べ物のもとをたどると植物にたどりつく
T:じゃあ、それでいこう
C:はい
ということで本時のまとめとして「食べ物のもとをたどると植物にたどりつく」に決まりました。
理科の用語を抑える
T:そしたら理科の言葉を確認します
C:はい
T:まず1つ目。生き物同士の「食べる」「食べられる」という関係は、くさりのようにつながっています。くさりっていうのはこんなやつね
C:う〜ん
T:まあ、くさりのようにつながっているの
T:ほんで、このような生き物同士のつながりを食物連鎖といいます
C:食物連鎖
T:じゃあ、ノートにかくよ
C:はい
C:かけました
T:ほんで、これが植物で、シマウマとか植物を食べる動物のことを草食の動物っていいます
C:草食の動物
T:ほんで、ほかの動物を食べる動物のことを肉食の動物っていいます。
C:肉食の動物
T:これらはとても大事な理科の言葉なのでおさえてください
C:はい
ふりかえりをする
T:じゃあ、ふりかえりをしましょう
C:はい
C:できました
終わりに
生き物の関係を図式化するとすごい見えてきます。やっぱり視覚情報って大事だなと思います。見えないものをみえるようにするために大事な手立てだと思います。また、調べるためのコツも教えることで情報活用能力も高まるかなと思います。
続きが気になる方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」指導案に悩む先生へ|4時間目の授業実践からヒントを!を御覧ください。
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「生き物どうしのかかわり」のまとめページをごらんください
🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。
▶3年生の理科授業まとめページはこちら
▶4年生の理科授業まとめページはこちら
▶5年生の理科授業まとめページはこちら
▶6年生の理科授業まとめページはこちら
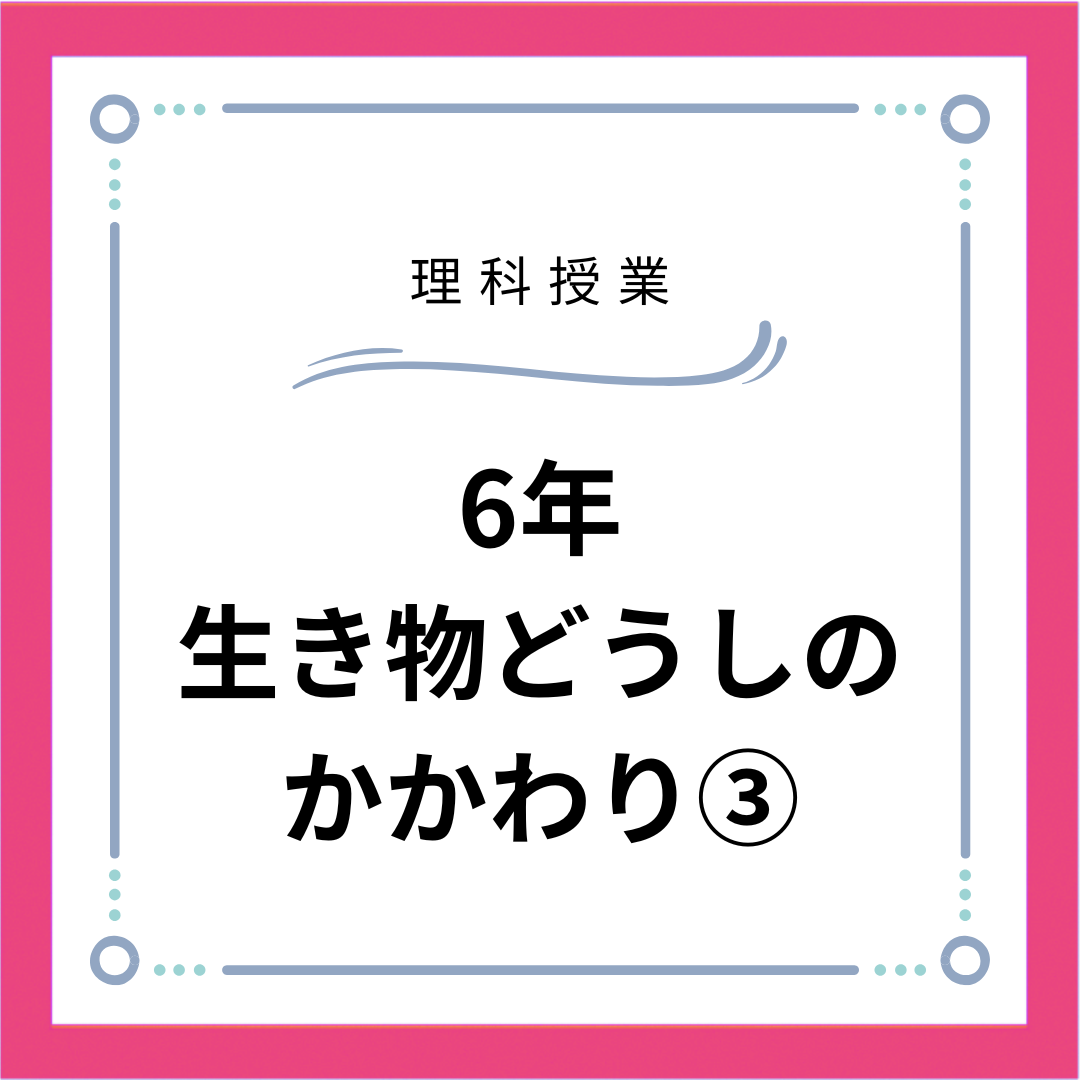
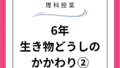
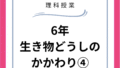
コメント