このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。
これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。
この記事を読むと、
・授業のねらいと展開の流れが分かります
・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります
・次の授業づくりのヒントが得られます。
学年別にまとめた授業案はこちら👇
👉 3年理科まとめページ
👉 4年理科まとめページ
👉 5年理科まとめページ
👉 6年理科まとめページ
この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「物のあたたまり方」のまとめページをごらんください
はじめに
この前の出張で理科の研究授業を見てきました。いろいろな学びがあったのですが、その中でも特に勉強になったのが、「単元を貫く課題を立て、それを解決するために学習を進めていたこと」です。
その授業者の実践に刺激を受け、自分も4年生の「物のあたたまり方」という単元で「学びのストーリー」に挑戦してみることにしました。
今回は、①この単元でやりたいこと、②単元を通して意識したいこと、③単元計画といった3つについて紹介します。そして、次回以降に個別の実践を出していこうと思います。
この単元でやりたいこと
この単元でやりたいことを一言で表すと・・・
金属、水、空気の温まり方のちがいを理解すること
だと思います。
日常生活の中で、子どもたちは金属、水、空気が温められることを理解しています。しかしながら、金属、水、空気の温まり方は目には見えないため、子供達は金属も空気も水も火に近いところから順に温まるイメージを持っていることが多いです。
実際は、金属は熱せられらところから順に温まっていくのですが、あたためられた水や空気は上に行き、動きながら全体が温まっていきます。こういった温まり方の違いを捉えられるようにしていくことがこの単元を学ぶ意義だと思っています。
単元を通して意識したいこと
上記であげたことをどの子も理解できるようにするために次のような工夫をしていきたいと思っています。
・温まり方は目には見えないため、予想の際にイメージ図を書かせる
・し温インクなどを用いて、視覚的に温まり方を捉えられるようにする
・共通点という考え方を用いて、金属、水、空気の温まり方を仲間分けする
今回は目に見えないものを扱うため、特に視覚情報が大事になるのではないかと考えています。また、この単元は日常生活と繋げやすい単元だと思っていて、そこも意識して指導していければいいなと思っています。日常生活のつなげ方としては、たとえば…
・料理で食材に火を通すにはどこにおけばいいかが分かる
・部屋を早く温めるために、エアコンの口の向きをどうすればいいかが分かる
・なぜコンビニのアイスコーナーは蓋がしまってないのか?
・熱気球はなぜ浮くのか
などが挙げられると思っています。こういったものとつなげることでこの単元を学ぶ意義を子どもたちに感じさせたいなと思っています。
単元計画について
単元計画については、下記のように考えています。
第1次 単元のゴール決め
・どこに食材を置くと火が通りやすいかクイズ
・金属、水、空気の温まり方が分かるとこのクイズが解けるようになるよ
<<金属、水、空気はどのように温まるのか?>>
第2次 金属の温まり方
<金属の棒はどのようにあたたまるだろうか?>
<金属の板はどのようにあたたまるだろうか?>
→金属は熱せられたところから順にあたたまっていき、やがて全体があたたまる
第3次 水の温まり方
<水はどのようにあたたまるのだろうか?>
→水は、あたためられると上に行く。水は動きながら全体があたたまっていく
第4次 空気の温まり方
<空気はどのようにあたたまるのだろうか?>
→空気は、あたためられると上に行く。空気は動きながら全体があたたまっていく
第5次 まとめ
これまでがくしゅうしたことをふりかえって、たしかめよう
終わりに
「勝負は、1授業目にあるのかな?」と思っています。自分の中では、結構いい流し方になったのではないかなと思っているので、ぜひ楽しみに待っていてもらえると嬉しいです。
続きが気になる方は、4年理科「物のあたたまり方」指導案に悩む先生へ|1時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。
この単元を最初から順に見たい方は、4年理科「物のあたたまり方」のまとめページをごらんください
🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。
▶3年生の理科授業まとめページはこちら
▶4年生の理科授業まとめページはこちら
▶5年生の理科授業まとめページはこちら
▶6年生の理科授業まとめページはこちら
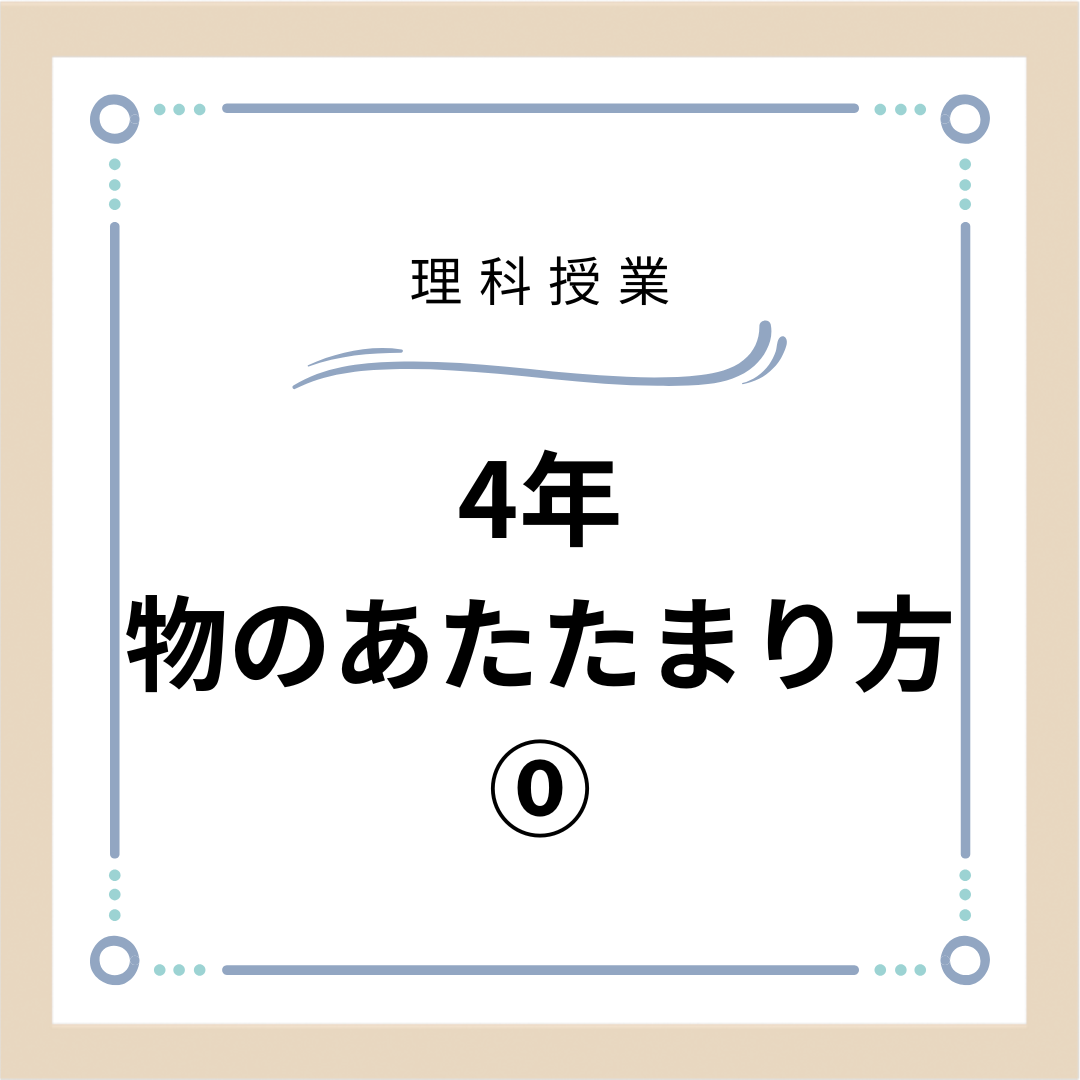


コメント