このブログ「ぼん先生の理科授業」では、理科専科としての経験や個人的な授業研究をもとに作成したセリフ形式の理科授業案を紹介しています。
これまでに約300本の授業案を公開し、全国の先生が「明日からすぐに実践できる理科授業」を目指して、発問例・板書・展開の流れをまとめています。
この記事を読むと、
・授業のねらいと展開の流れが分かります
・子どもが考えやすくなる発問例が見つかります
・次の授業づくりのヒントが得られます
学年別にまとめた授業案はこちら👇
👉 3年理科まとめページ
👉 4年理科まとめページ
👉 5年理科まとめページ
👉 6年理科まとめページ
まだ1授業目を見ていない方は、先に6年理科「動物のからだのはたらき」指導案に悩む先生へ|1時間目の授業実践からヒントを!をご覧ください。
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「動物のからだのはたらき」のまとめページをごらんください
<吸う空気と吐き出した空気は同じか?>
板書案

振り返りをして、課題を掴む
C:前の学習のふりかえりをしましょう
C:はい
C:Aさん
C:はい。前の課題は、「吸う空気と吐き出した空気は同じか?」です
C:同じです
T:そうだね。吸う空気って何がどれだけあるの?
C:窒素が78%、酸素が21%、二酸化炭素が0.04%です
T:そうだね。じゃあ、これの割合は同じなのか、違うのかを調べるために、何使って実験したかと言うと
C:気体検知管
T:ですね。じゃあ、今日は何をするかと言うと
C:結果をみて、考察する
T:そうだね。じゃあ、課題は前回と同じでいいですか?
C:はい
といって、本時の課題として「吸う空気と吐き出した空気は同じか?」に決まりました。
結果を確認する
T:そしたら、まずは酸素です。酸素はこうなりました。
C:お〜
T:いくつくらい?
C:18%
T:ですね
T:ほんで、これが二酸化炭素。
C:3%だ
T:ですね
T:じゃあ、結果に書きましょう
C:はい
結果から言えることは?
T:そしたら、今回考察書いていたら時間がかかりそうなので、省略バージョンにします。この結果から言えることはなにかについてノートにかいてみて。
C:はい
C:できました
T:おしえて
C:はい
T:Bさん
C:はい。吸う空気と吐き出した空気は同じではないです
C:同じです
C:ほかにあります
C:Cさん
C:はい。酸素が減っているので、人は酸素を取り入れているとわかりました。
C:同じです
T:酸素って全部取り入れているの?
C:いや、全部じゃない。
T:そうだよね。でも、人は酸素を取り入れているだと全部みたいな感じがするんだけど
C:あ!酸素の一部だ!
T:そうだね。そのほうがいいね。ということで、人は酸素の一部を取り入れている。まだ、他に意見はありますか?
C:はい
T:Dさん
C:はい。人は二酸化炭素を出しているです
C:同じです
T:そうだね。ということは、人は何を取り入れて、何を出しているの?
C:酸素の一部を取り入れて、二酸化炭素を出している
T:ですね。だから、吸う空気と吐き出した空気は別物だよってことだね
T:ちなみに、本当に二酸化炭素が増えているのか別の実験で確かめることもできるよ。何をつかえばいい?
C:石灰水
T:そうだね。ということで、サクッとしましょう
C:はい
T:集合。
C:はい
T:そしたら、ナイロンに、石灰水をいれ、息をはきます。ほんでこれをふると
C:お〜白く濁った。
T:そうだね。こんなふうに、気体検知管でも石灰水でも、調べると二酸化炭素が増えているっていうのが説得しやすくなるね
C:はい
まとめをし、呼吸についてしる
T:じゃあ、まとめをしましょう。今日のまとめはどうする?
C:吸う空気と吐き出した空気は同じではない
T:じゃあ、それにしよう
ということで、本時のまとめとして、「吸う空気と吐き出した空気は同じではない」に決まりました。
T:そしたら、大事な理科の言葉をノートに書きます。
生物が、酸素を取り入れて二酸化炭素を出すことを呼吸という
C:できました
T:ということで、ラジオ体操とかで深呼吸する場面もあるけど、これからは、あ〜自分って今酸素を取り入れているんだな。あ〜自分って今二酸化炭素を出しているんだなと思いながらしてください
C:はい笑
T:じゃあ、一旦振り返りをしてみて
C:はい
C:できました
呼吸の仕組みを知る
T:さあ、じゃあ息を吸ったあとって体の中で一体何が起きているんだろうね。
C:う〜ん
T:ということで、呼吸の仕組みについてサラッと確認をしよう
T:じゃあ、ワークシートを配るね。もらったら名前をかいてね
C:できました
T:そしたら、まず、空気はどこから入るかって言うと2パターンあります
C:鼻と口
T:そうだね。ほんでね、鼻や口から入った空気は、気管を通ります。気管っていうのはここのこと
C:はい
T:ほんで、ここにもう一本あるよね。これは食道っていいます
C:あ〜聞いたことある
T:ほんで、気管のあとは、肺に行きます。ちなみに肺は何個ある?
C:2つ
T:そうだね。右と左にあります
T:ほんで、このあと、酸素の一部が肺の中の血管を流れる血液の中に入ります。要するに、酸素は必要だから体の中に入るってことね。
C:なるほど
T:血液ってわかる?
C:血
T:そうそう。あれの中に酸素が入り込むの。ほんで、その酸素は、体が活動するときに必要なので、全身に運ばれます。
C:はい
T:ほんで、たとえば、手に酸素が来たとして、その酸素をつかって活動すると要らなくなったものが発生します。その一つが二酸化炭素になります。二酸化炭素はいらないので、その二酸化炭素は血液にはいります。ほんで、肺にいったら、血液から二酸化炭素が渡されます。
C:ほう
T:そしたら、この二酸化炭素はいらないものだし、外に出したいので、どこ行くかって言うと
C:気管
T:そうそう。ほんで、その次は
C:鼻や口
T:そう。ほんで二酸化炭素は出されるってわけ
T:じゃあ、今の話を踏まえて、ワークシートのカッコの中埋めてみようね
C:はい
C:できました
T:じゃあ、呼吸のとき大活躍しているのは何ていう臓器かっていうと
C:肺
T:正解。この肺の働きで、酸素と二酸化炭素をやりとりしてくれているというわけ。じゃあ、肺の役割をかくよ
肺…空気中の酸素の一部を血液に取り入れ、血液から二酸化炭素を外に出している
C:できました
T:ちなみに、教科書には他の動物についても載っています。気づいたことをペアで相談
C:はい
C:できました
T:じゃあ、おわりましょう
終わりに
気体検知管をつかって、酸素が減って、二酸化炭素が増えることは目で見てわかるのですが、そこの意味理解(人は酸素を取り入れているからへっている。二酸化炭素はいらなくて吐き出しているからふえている)がしっかりできるようにしてあげたいです。
それをスムーズにするためには、前時の予想のときにサラッとふれておくことが大事なんだと思います。「種を蒔く」「仕掛けておく」って表現で、昔教えてもらったのですが、そういう仕掛けがたくさんあるとどれかとつながって、ポンと子どもの中に落ちるんだろうなって思います。
続きが気になる方は、6年理科「動物のからだのはたらき」指導案に悩む先生へ|3時間目の授業実践からヒントを!をごらんください。
この単元を最初から順に見たい方は、6年理科「動物のからだのはたらき」のまとめページをごらんください
🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。
▶3年生の理科授業まとめページはこちら
▶4年生の理科授業まとめページはこちら
▶5年生の理科授業まとめページはこちら
▶6年生の理科授業まとめページはこちら
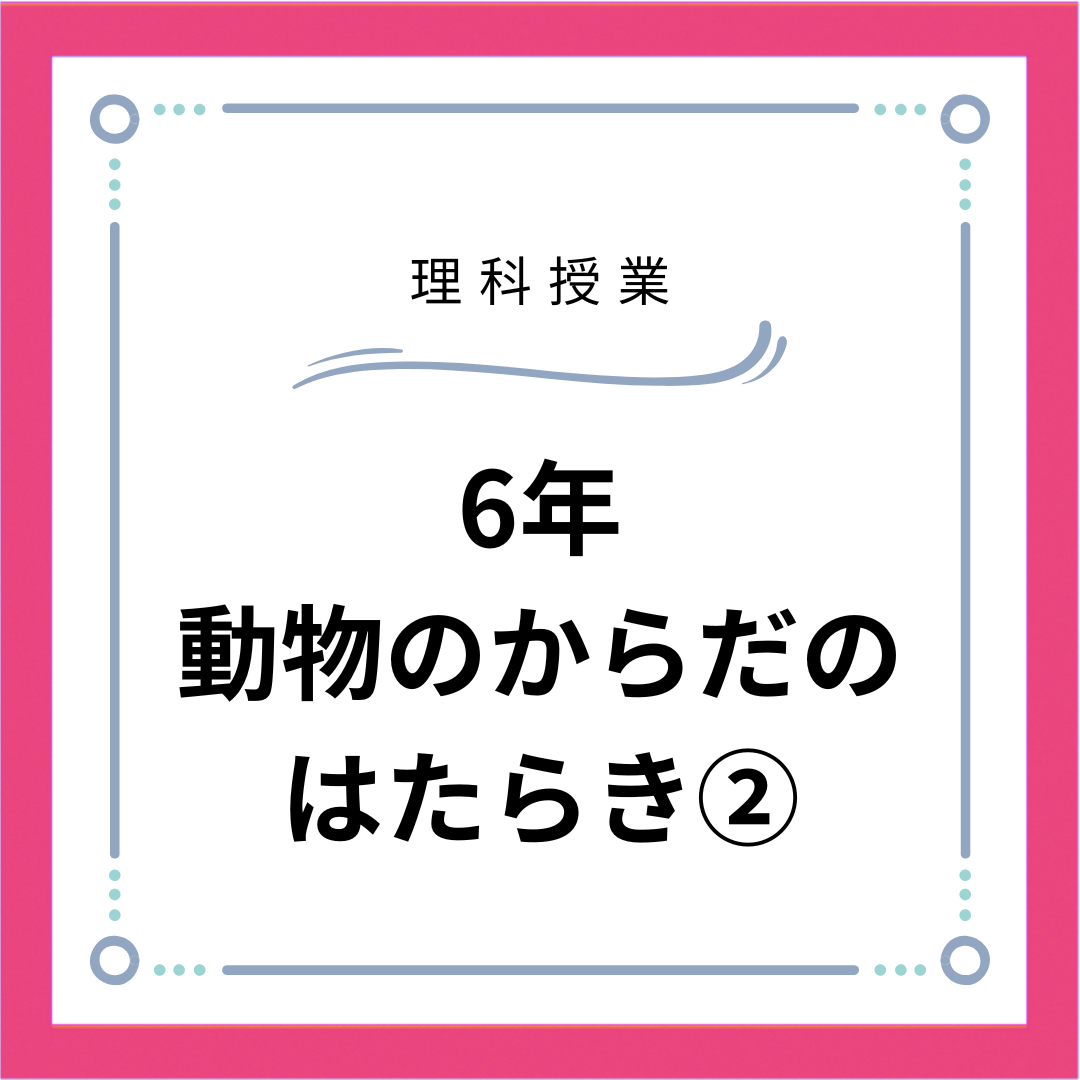

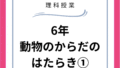
コメント