自由研究の指導について
今日のテーマは、「自由研究の指導」です。先日、こんなメッセージをいただきました。
いつも参考にさせていただいてます。
私は、今年からはじめて理科を持ったのですが、自由研究の指導の仕方がよくわかりません。
何かコツとか気をつけていることはありますか?ぜひ教えてください。
自分もはじめて理科を持ったときは、自由研究の指導って何をすればいいんだろうってなやみました。今も悩みますが…笑
せっかくメッセージをいただいたので、自由研究の指導について紹介をしたいと思います。
1授業の中でやるべき4つのこととは・・・
まず、夏休み間際は、成績処理にバタバタしていて、時間の確保がなかなか難しいと思います。そのため、自分は基本的には1授業で教えます。
1授業で教えるとなると、当然ですが、教えることは絞らないといけません。だからこそ、ぼん先生は…
①理科という教科はどんな教科なのかを確認する
②研究の流れを確認する
③研究の流れを具体例を踏まえて確認する
④見本を見せる
っていう4つのことにしぼって指導をします。
「①理科という教科はどんな教科なのかを確認する」について
まず、はじめにこういったやり取りをします。
T:まずはじめに、確認するんだけど、理科ってどんな教科?
C:うーん
T:4月にいったんだけどな
C:あ!不思議を自分の手で真実に変える教科
T:すごい!正解
T:そうなの。理科って不思議を自分の手で真実に変える教科なんだよ。ほんでね、今までは先生と一緒に不思議を見つけたり、実験したり、考察したりしていたよね
C:はい
T:でもね。自由研究は先生の力を借りずに、やるの
C:え〜できません
T:そっか。気持ちはわかるよ。でもね、みんなは少しずつ力がついてきたし、自由研究できる子はおると思うよ。あとね、たとえかんぺきじゃなくてもいいの。挑戦することが大事だと思う。そうすれば、絶対に理科のちからは上がっていくよ
C:そっか
T:あとね、自由研究は自由だから、自分の見つけた不思議に挑戦してもいいの
C:え!
T:たとえば、どうすれば割れないシャボン玉ができるのかな?っていうのを調べていた子もいたよ
C:え!それおもしろそう
T:でしょ。まあ、とりあえず、自分で見つけた不思議に対して、「真実はこれです」っていうのを出せたらOK。軽い気持ちでやってみようよ
C:ちょっとやってみようかな
このやり取りをする目的は、「自由研究も普段の理科の授業と同じで、不思議を真実に変えるものだよ」っていうのを確認することになります。
自由研究でよくあるのは、「図鑑で調べてわかったことをまとめただけのもの」です。これ図鑑で調べること自体は悪くないのですが…なぜ図鑑で調べるのかがぬけているんです。どういうことかというと
◯ 不思議を解決するために、図鑑で調べてまとめ、真実をはっきりさせる
✕ 図鑑でまとめる(不思議とか真実とかは意識してない)
ってことです。これを防ぐために、まず大前提を抑えないとだめってことになります。
「②研究の流れを確認する」について
つぎにこんなやり取りをします。
T:そしたら、不思議を自分の手で真実に変えるためにはどういう流れを意識するといいかってわかる?
C:うーん
T:まずは1番目、「不思議を見つける」です
C:あ〜
T:2番目
C:予想をする
T:正解。3番目
C:実験方法を確認する
T:正解。4番目
C:実験する
T:そうだね。まあ、「観察する」とか「本で調べる」もそうだね
T:つぎは?
C:結果をまとめる
T:そうだね。次は?
C:考察する
T:そうだね。ここで真実がはっきりするわけだね
C:はい
T:つぎは?
C:ふりかえりをする
T:そうだね。新しい疑問とか、新発見したこととかをまとめればいいね
C:はい
T:すごい。よくわかったね。
C:だって、普段の理科の流れとおなじだから
T:そうそう。自由研究だけど、普段の理科の授業の流れと変わらないよ
このやり取りをする目的は、「自由研究も普段の理科の授業と同じようなステップで真実を発見すればいい」っていうのを確認することになります。
何をすればいいのかって見通しが持てないとつらいじゃないですか。だから、「これをしたあとは、これをすればいい」っていうのを見える化してあげるといいなって思います。
「③研究の流れを具体例を踏まえて確認する」について
次にこんなやり取りをします。
T:どう?できそう
C:さっきよりは
C:ぼくは無理かも
T:そっか〜。じゃあ、ちょっとこの流れを意識してみんなでやってみよう。そしたら、やり方がもっと分かるかも
C:はい
T:そしたら、今回はこんなものをもってきました
このやり取りをする目的は、「研究の流れを踏まえて、具体的に研究の仕方を確認する」ということになります。
自分は、何かを理解するときって、「具体と抽象」を往還することが必要だと思っています。「具体と抽象」っていうのは、例えば・・・
抽象:頭、胸、腹があって、胸から足が6本出ている
具体:あり、チョウ、ばった
のことを指します。具体と抽象を往還することで、「くもはちがう」など、より抽象の方の意味を理解できるようになると言った感じです。自由研究の指導もそうで、「研究の流れ」と「実際の研究」を往還することでより深く理解できると思っています。
ほんで、この時の題材なんですが、自分は、本校で使っている理科のテストのEXテストを参考にしてやっています。これをする理由は・・・
①時短になる・・・EXテストってこれは指導しておかんとだめっていうのはあると思っています。そのため、EXを題材にするとそれの指導と自由研究の指導が一気にできます。これめちゃくちゃおすすめです
②題材選びが困らなくなる・・・EXテストってそれぞれの学年で学んだ分野から出るので、実態にあっています。また、わざわざ自由研究の指導のためにネタを集める必要がないので楽です。
といった2点がにあげられます。
「④見本を見せる」について
最後にこんなやりとりをします
T:どうけ?
C:なんか、できそうです
T:そっか!ならよかった。
T:ちなみに去年の3年生はこんなのしてたよ
C:へ〜
(見る時間をとる)
T:ちなみに、去年の3年生は、「自由研究をするときに参考にしたかったらしてもいいですよ」っていってたよ
C:え〜ちょっとやってみようかな
T:そうそう。まずは、やってみればいいよ。もちろん、先生も学校に来てもらえば、相談にはのるし、お家の方に相談してもいいと思うよ。まずは、やってみる。やってみないと絶対にできるようにならないから。
C:はい
このやり取りをする目的は、「自由研究の完成品のイメージをもたせること」「助けてもらえる環境があることを知ってもらうこと」になります。
「自由研究って難しそう」って思いはだれにでもあると思います。でも、そういった思いを緩和させ、「ちょっとやってみようかな」っていう思いにさせるには、「安心感をあたえること」が大事だと思います。
終わりに
いかがだったでしょうか?自分はこの4つを意識して教えています。まずはやってみる。これが何事においても大事だと思います。
自由研究のレベルをつい求めてしまうけど、そうじゃなくって「やってきた時点で100点」「不思議を真実に変えられたから良い研究だね」っていうように基準をグッと下げてあげることが大事だと私は思います。
少しでも参考になれば幸いです。
🌱他の学年の理科授業まとめもご覧いただけます。
▶3年生の理科授業まとめページはこちら
▶4年生の理科授業まとめページはこちら
▶5年生の理科授業まとめページはこちら
▶6年生の理科授業まとめページはこちら
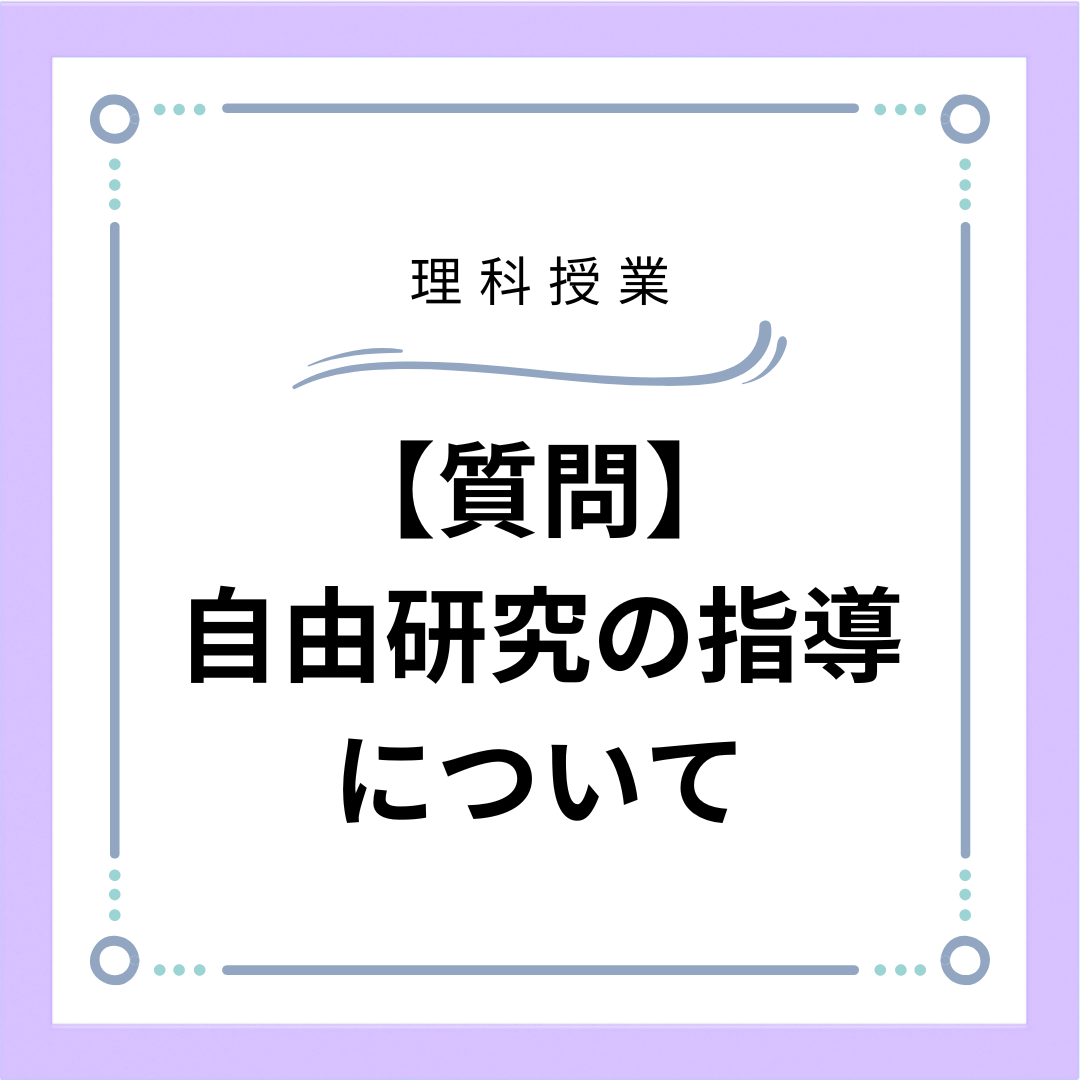

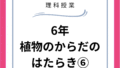
コメント